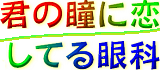令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
カテゴリー「医療訴訟」の記事
「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか? 」の第3章から第5章
2012年10月18日
さて、「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」 (貞友義典著・光文社新書)の続きです。第3章のタイトルは、『「大病院」は安全か』です。
最初の小見出しは、「大病院はリピーター医師の隠れ蓑」となっています。まず、医療ミスについて、ミスが起きるのは「低劣な知識や診療技術がその源」であり、「医師が必ずしも我々が思っている程のレベルにないこと、また必ずしも研鑚を積んでいないこと、さらに、研鑽を積むことが制度的に予定されていないこと」が医療界全体の問題だと述べられています。 確かに上を見ればきりがありませんが、この筆者の指摘は、医師と弁護士を入れ替えても同じことであるように思われます。研鑚を積む制度が貧弱であることについても医師と弁護士に共通していますが、医師にはそれでも初期研修がある上に、その後も研鑚を積むことのできる環境に留まれるのが普通であるのに対して、弁護士は新司法試験制度による法曹大量排出の影響で、司法修習が終了した後に、少なからぬ新人弁護士が事務所への就職もままならず、よって研鑚を積めぬまま独立せざるを得ないようです。実際に能力的にかなり危ない弁護士が増えているように見受けられ、問題がより深刻に思われます。また筆者は、『「大病院の医師だけは違う」などということは絶対にあり得ません。』とも述べていますが、これについても弁護士に当てはめて考えると、大規模弁護士事務所の弁護士なら優秀、とは直ちには言えないことと似たようなものに思われます。
次の小見出しは、『無能な医師はミス隠しのため「たらい回し」に』とあります。裁判官の異動も、システム的には違う部分もあるのでしょうが、類似の効果が発揮されているように思いますが如何でしょうか。
当てこすりはとりあえずこれくらいにして、次の「大病院のシステム上の問題」という小見出しの項については、まじめに見てみたいと思います。まず(1)として、麻酔科医の不在の手術の問題を挙げられており、これは御説ごもっともなのですが、どのようにして実力ある麻酔科医を増やすかという医療界内の問題が絡むので、とりあえず措いておきます。次に(2)として、検査結果の確認・告知システムの不備の問題が取り上げられています。かつては、検査で異常値が出ても、患者さんが受診しなければ伝えられることがないシステムが当たり前であったように、この問題点は確かにシステム上の不備と医療関係者の意識の低さを反省すべき点だと思います。このような医療そのものとは別のアプローチで解決できる問題については、非医療者からも大いに声を上げて頂くのが良いと思います。続く(3)では、鉗子分娩用の鉗子を置いていない分娩室の問題を扱っています。出身大学によって鉗子分娩の技術習得機会に大きな差があるが、鉗子分娩を習得できないことは問題だというようなことを述べられていますが、それこそ医学的・医療的問題に医師の裁量が加わる問題であり、弁護士が数人の協力医の意見を元に、現状を超越して医療水準を語ることは適切でないだろうとだけ指摘しておきます。
第4章は「改ざんされるカルテ」と題して、揉め事になった場合に医師がカルテを書き換えたりするなどの問題を批判しています。このことは筆者が主張するように、昔であると問題が起こった場合に、医療側がなんとかごまかそうとすることは少なくなかっただろうと感じるところであり、これを追求してきた人々には敬意を表したいと思います。その点は肯定した上での話になりますが、医療裁判を見ていて気になることは、原告側が都合のいいことだけを並べたり、事実を誇張したり、ごまかしたりする例も実は結構多いということです。もっとも医療側にしても、都合の悪い部分については、原告側から指摘がない限り黙っていることは今でもしばしばあります。その場合、結局裁判では真実が明らかにならず、裁判での解決の限界を感じるところです。とはいえ、裁判において自己に都合のいいことばかりを述べ続けることは、医療裁判に限らず一般の民事裁判では当たり前のことなのであって、医療裁判に限って無邪気に医療側にばかり誠実さを求め、それがなされないからといって憤り続けていては、永遠に解決を見ないのではないかと思います。
それにしても、「カルテ改ざんはやりたい放題」との小見出しの下に書かれた、以下の部分は大いに引っかかります。
テレビドラマの『白い巨塔』の中に、国立大学の浪花大学病院で、弁護士同席のもとに事故調査会が開かれ、医局ぐるみでカルテ改ざんに走る場面がありました。私がこの場面を見て最初に思ったことは、どこかの大学病院からフジテレビに対し、「非現実的だ」「視聴者に誤解を与える」という抗議が行くだろうかということでした。しかし、そのような抗議があったとは聞いていません。ということは、日本ではあり得る、現実に行われていることだ、ということなのでしょうか。そうだとしたら恐ろしい話です。
これは・・・どうでしょうかね。番組に抗議があったとしても、そのことをテレビ局がいちいち公表するとは考えにくいですから、「抗議があったとは聞いていない」からといって実際に抗議がなかったことの証明にはならないでしょう。それなのに、「ということは日本では現実に行われている」と仮定し、「そうだとしたら恐ろしい」などとの感想を書くのは、いくら仮定での話とはいえ、その仮定の根拠が弱いものであることを考えると、ちょっと我田引水に過ぎるのではないかと思うのですが。
第5章は「鑑定について」となっています。最初の小見出し「鑑定人が決まらない」では、鑑定人選びが困難だった例として、筆者が経験したという、以下のような例を紹介しました。
被告の鑑定申請があり、裁判所が七人の医師を候補に挙げました。原告代理人の私は、そのうち二人を鑑定人として(実は渋々です)了承し、他の五人については絶対に反対と意見を述べました。そうしたところ、被告病院側は、全く逆に五人を可とし、私の了承した二人を絶対反対と上申したのです。裁判所が頭を抱えてしまいました。
これを普通に読めば、この事例で鑑定人選任を困難にした責任の割合は、どちらかと言えば原告側、つまり筆者のほうが大きいように読めてしまいますね(笑)。5対2で、しかも承諾した2についても渋々だというのですから。
また、鑑定書に似たものとして、私的意見書があると書かれています。この私的意見書は、原告なり被告なり、一方の依頼を受けてそれに協力する医師が書き、その依頼した側が提出するものなので、提出する側に有利な内容が書かれているのが当然であり、「わざわざ自分たちに不利な私的鑑定書を出す馬鹿はいない」とまで書いています。しかし、医療訴訟ではこの例のように原告側が自ら不利になるような意見書を出した例もあることにはあり、「わざわざ自分たちに不利な私的鑑定書を出す馬鹿」の表現は、その通りといってしまえばそうかも知れませんが、もうちょっと理性的な書き方があったのではないかとも思います。
「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」の第2章
2012年10月3日
昨日読み始めた「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」 (貞友義典著・光文社新書)の続きです。
第2章も冒頭からものすごい勢いです。まずは運転免許と医師免許を対比させることからはじまります。
運転行為は、事故が起きれば自分も危険にさらされるので運転者も注意するが、医療行為はそうではない、だからこそ医療行為の方がより重い責任を科すべきだそうです。なるほどとも思われますが、では法律家のミスによる人権侵害についてはどうなんでしょう。重い責任を科されているでしょうか。
「医師を甘やかす医賠責保険」(医療賠償責任保険)という小見出しの項では、「医師が自腹を切ることはまだまだ少ないと言っていいでしょう」などとして、賠償責任を負っても自腹を切らないで済むことを問題視しているようです。しかもその同じ項では、高額の保険に加入することは被害者救済のために必要だとも述べており、結局何が言いたいのかよくわかりません。某県医師会長が、「保険料が1日当り63円で、居酒屋の焼き鳥1本より安いので加入すべき」旨を述べたことまで取り上げていますが、はっきり言ってどうでもいいことで、むしろ焼き鳥と対比をさせるという医師の庶民感覚を汲み取ってもらいたいものです(笑)。
賠償金についてはさらに続きます。ある産科の事件で医師が責任を認めて全額自腹で払ったことがあったそうなのですが、その医師は賠償金を用意するために、不動産を担保に借り入れたというのです。示談が終わり夫妻の家を出た医師に対して、激励をいい忘れたと家を飛び出す夫を筆者が見て、胸がこみ上げてきたというのですが、そのこみ上げてくるものを得た源泉に、不動産を担保に借金をした医師がいたことにどれほど心を致したか、気になります。これが美談なのであれば(確かに美談ですが)、悪意のない交通事故で過失責任を負ったら、全財産を投げ売って賠償することも美談だということなのでしょう。なんだかなぁ、と思います。
さて、裁判になった場合、法律家以外の方はご存じないかも知れませんが、担当医が法廷に出かける必要があるのは、通常は尋問を受ける当日の1回だけです。それは法律家から見れば当然のことなのですが、筆者はどういうわけかこれを問題視しているようなのです。さらに、「どうして被害者や遺族が証言をするときにそれを法廷で聞いてくれないのか」とも書かれています。それを聞かずに帰ることを問題視して、「被告医師は自分の尋問が終わればさっさと帰ります。なぜ、さっさと、そして場合によってはこそこそと帰ってしまうのでしょうか。」などと書いて、終了後の行動にまでケチをつけているのです。そういう一方でその直後には、医師が自分の尋問が終わった後にも帰らずに、「ふてぶてしく笑いながら原告本人の尋問を聞いているのも困ったもの」と述べており、ここでも何が言いたいのかよくわからないのです。ちなみに私がこれまでに傍聴した事件の中には、どう聞いても原告側の言いがかりであり、その通りに原告敗訴となっている事例が多々あります。特にそういう類の事件の場合は、筆者が問題視するような行動を訴えられた医師が取ることがむしろ当然と言えるでしょう。そういう事例も多々あるのです。
ちなみに、裁判官が明らかな誤りを犯したこと(例えば一宮身体拘束裁判のような)に対して無理を承知で提訴をしたら、その訴えられた裁判官はどうなるでしょうか。裁判の第一回目は訴えられた側は欠席が許されているため、「責任がない」旨を記した定型的な書面を提出します。そしてその提出によってその裁判の審理は終了し、次回は判決となります。しかし判決の日は訴えた側も訴えられた側も出席する必要がないので、訴えられた裁判官は欠席して終了、もちろん勝訴するのです。
ミスを繰り返しても医療賠償責任保険料の増額がないことも問題だと言います。確かにこの点は一考の余地があるかも知れません。しかしこの点はよく検討しないと、不成功に終わりやすい難症例でも、失敗したら保険料が上がるので手を出さないという医師が増えるかも知れず、却って社会の不利益に繋がる可能性もあるでしょう。ともあれそのような難しいことはさておき、『なぜこんなに甘やかすのでしょうか。なぜこんなに特別扱いをするのでしょうか。こんなに甘やかしていれば、「ミスをしても痛くも痒くもない。どうせ保険会社が全部やってくれる」と考えるだけで、反省などありません。』などと断定するのは如何なものでしょうかと言いたいです。
医師免許は取消されることがほとんどないことも問題視しているようです。しかしこれなどは、法曹資格の取り消しについてはどうかを考えれば、「おまえが言うな」の極致でしょう。「これらの実情を知るにつれて、このままでは医療ミス自体を減らすことはできないし、ミスを繰り返すリピーター医師もまたどんどん増えるに違いない、という確信に近いものを感じるようになりました。」といいます。そうであれば、弁護士についてもいろいろと甘いところがあるので、ミスとまでは言わずとも、問題弁護をする弁護士は増えていくように想像していますがいかがでしょうか。
ミスを犯した医師に、再研修制度がないことも問題だと言います。医師免許の更新制度がないことについては触れられているだけでしたが、筆者は他所で意見を述べられているようです。確かにこれらについては検討を要するものだと思います。法曹資格にも再研修制度と更新制度がないことを考えれば、なおさらそのように思います。
他にも細かいことがいろいろと書かれています。医師が原因不明と説明することが多いことについて、『世の中に「やることはきちんとやったが原因不明」なことがそんなにたくさん起きるとは思えません』などと述べていますが、これなどは私に言わせれば医学を甘く見ているのではないかと疑わせる発言であり、「あなたは医学に対してもそのような前提で、医療訴訟を受任しているのか」とひとこと言いたくなります。
「大きなミスを犯したら、もう医師としてやっていけない、というくらいの緊張感がないと、不勉強な医師はいつまでたっても不勉強なままです。」とも書かれています。私も、不勉強な患者側弁護士に緊張感を与えられるよう、より一層、無限大の厳しさで法廷を見つめていこうと、この本を読んで決意を新たにする次第です。
ちなみにここまで読んでも、まだこの本の半分に達していません(笑)
「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」という本
2012年10月3日
自分のサイトに、「リピーター弁護士」という記事を書こうと考えているのですが、その下敷きとして読んでおかねばならないだろうと思い立ち、「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」 (貞友義典著・光文社新書)の古本を1円(送料別)で購入しました。
まだ1章しか読み終わっていませんが、もうゲンナリしてきました。第1章は「リピーター医師の誕生」というタイトルになっています。
不勉強な医師、過ちを犯す医師を徹底的に叩こうという意気込みのようです。確かに医師は勉強すべきですし、過ちは謙虚に反省する資質も必要でしょう。しかしそういう法律家はどうなのでしょうか。一言で言えば、「どの口が言うか」の心境です。
添付文書・厚労省の医療安全局通知を読まないまま、知らないまま投薬をする医師がいると咎めています。では医療訴訟において最も重要である最高裁判例を知らずに提訴を受任したこの話はどうなんでしょう。
抗癌剤の用法を誤った悪魔の治療計画を咎めています。では主張内容の見通しも立てないまま提訴を受任したこの話などはどうなんでしょう。
有罪となり刑事罰が科せられた事例について、量刑判断が軽いと咎めているものもあります。では弁護士の懲戒制度はどうですか?医療事故で刑事罰が当たり前なのであれば、弁護士がうっかりして印紙代を払い忘れたり、控訴期間を逃して控訴できなかった例などは、依頼人に対する人権侵害であり、刑事罰に問われても良いくらいだと思いますがね。
能力のない医師を咎めています。では提訴から3年半、沖縄と兵庫を往復するばかりで、なんの仕事をしたのかよくわからないこの事件の原告代理人はどうなんでしょう。高校数学の内容を理解できなかったこの事件の裁判官や、中学数学の内容を理解できなかったこの事件の裁判官はどうなんでしょう。
これほどの医師叩きの本が、弁護士によって当然の正義であるかのように書かれているところを見ると、私の法曹批判などまだまだ甘いものだと感じざるを得ません。そうでなくても医師の業務は、ミスがあって結果が悪ければ、民事責任はおろか刑事罰ですら容易に問われるものなのですから、その責任判断を司る法曹に対しては、その行いが暴走していないかを含めて、さらなる強力な批判的な眼を向けてやる必要があると考えて良いように思われました。
「リピーター弁護士」についても、遠からず記録してみたいと思います。(後日注:その記事として「リピーター弁護士 なぜムリを繰り返すのか?」をアップし,本記事中にもリンクを設定しました。)
加藤新太郎裁判長の訴訟指揮その3
2012年9月28日
いつものように東京高裁・地裁に出かけて開廷表を見ていると、高裁の開廷表に、地裁で傍聴した事件の控訴審第一回弁論の表示が。控訴審事件番号は平成24年(ネ)第4200号。法廷に入って待つこと数分、お出ましになられたのは加藤新太郎判事… そうか、そういえば22民事部でした。例によって早口ですから、メモは大雑把です。
加藤裁判長「被告病院の応答が、裁判所から見るとやや物足らない。基本的には新しい主張は出てこないので、控訴人は証拠弁論を一所懸命している。被控訴人としては、いちいち『これは当たっている』『当たっていない』という主張をしてもらいたい。」
ふーむ、「証拠弁論」といういい方をするんですね。
加藤裁判長「例えばリスク評価。控訴理由書では原判決の○○について、『証拠を記していない、認定が間違っている』としている。こういう点は簡単に反論できる。○○証人についての評価は反論できる。『弱いリスク要因でも複数重ねれば高リスクであることを認定できる』とあるが、これもそうは言えないのか、その指摘を。○ページ、『人種差によるリスク。白人なのでリスクを1段階上げる』とあるが、これに対する反論は出てきていない。」
加藤裁判長「国枝医師の意見書について、答弁書では『国枝医師が、従前、論法に書いていたのは肺血流シンチ云々…今回はCTと書いている。従前のと言っていることが違う。だから信用できない』とあるが、それは、言い過ぎでは?」
加藤裁判長「鑑定をやらなくても明々白々なら、鑑定をやらないこともいくらでもありますよ。なんでも勝つわけではないからね、医療裁判は。」
と、バッサリ。
亡くなった患者さんの肺塞栓症の重症度が争点の一つで、控訴人はひどかった(massivだった)と、被控訴人はそれほどでもなかった(massivではなかった)と主張しているのですが、
控訴人代理人「国枝医師が massivと判断している。」
被控訴人代理人「詰まった度合いで massivか否かを判断するのではない。」
控訴人代理人「国枝医師も、CTだけで重症度判断をするとは言っていない。」
被控訴人代理人「甲B15号証で臨床所見を上げているが、それ自体がガイドラインの『血行動態不安定』に当たらない。甲B115号証では、『とにかく詰まり具合で見るのだ』書いている。」
115号証って、聞いただけでもウンザリですね(笑)
控訴人代理人「本件では70%詰まっている」
加藤裁判長「尋問の聞き方が悪かったからしょうがないね、という話になりがちですよ。」
あああ、この場に原告本人もいるのに…(笑)
加藤裁判長「5年間で20回の争点整理。最初に主張した過失と構成を途中で変えていて、それで負けている。控訴審でもまた総花的な主張をしている。控訴審ではここを見て欲しいというところをはっきりしないと、原審を全部引用して敗訴になってもおかしくないですよ。」
この点私は、控訴人代理人の一人である伊藤紘一弁護士が、以前にも素人目にはハチャメチャな主張を展開していたのを聴いたことがある(「行き当りばったり提訴医療訴訟事件」として既報)ので、傍聴席で苦笑しながら聴いていました。
ところで、司法判断の方法にもガイドラインのようなものがあって、優秀な判事さんだとそういう”ガイドライン”をしっかり踏まえて審理されますが、中には相当にひどい審理がされている事例もあるわけです。そのことを考えると、医療行為についてやれガイドラインを外れていないかとか適用を誤っていないかとかを、所詮は医療の素人である法律家が過度に厳密に審理するのは、滑稽といえば滑稽です。「沖縄総胆管結石摘出不成功訴訟」に見られたような訴訟指揮のレベルの仕事を、医師が医療行為において行っている場合であっても大目に見ろとまでは直ちには言いませんが、今回報告した事例に限って言えば、亡くなった患者さんの医学的所見を相当に穿った見方をしてして初めて、原告の主張するような過失の判断を検討する余地が生まれるという状況であると思われるところ、原審では『普通に考えればハイリスクではなく、血栓症はmassivではなく過失もない』という判断をしたのですから、それこそそのまま引用して控訴人ら敗訴としてもいいのではないかと思うわけですが、控訴審の裁判長が優秀かつ緻密だと大変ですね(笑)
ソウル中央地裁で医療専門審理委員尋問を傍聴
2012年9月26日
2012年9月21日にソウル中央地裁で、医療訴訟の専門
概要は、77歳女性、10年前に脳梗塞の既往あり。高血圧、高脂
手術翌日のCT画像(これはおかしいということになってから撮られたもの)では、出血はかなり広範囲だが、眉毛部から結紮
原告側の主張は、
コイル塞栓術が良かったのではないか?
経過観察でも良かったのではないか?
コイル塞栓術の話は聞いておらず、説明義務違反では?
複数の脳動脈瘤を一度に結紮するのは不適切では?
術後出血は、手術中に牽引しすぎた過失があってのことでは?
術後出血に対する治療内容が不適切だったのでは?
といったところのようですが…
うーん、コイル塞栓術の説明をせずに自己決定権を奪ったとは言っ
… orz
何科であるかはその場では把握されておらず、答えはありませんで
ちなみに専門審理委員に対する尋問は、まず原告代理人、次に被告
1時間半の尋問終了後に、案内してくださった書記官さんが「長時
専門審理委員制度は日本でできてから韓国に導入された制度で、日
あと、原告代理人は、韓国の尊厳死事件で原告代理人をした事務所
とはいえ、第三者医師に率直に意見を求めることができるのは、双
(韓国の尊厳死裁判:尊厳死を認めさせることを求めて大学病院を