令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」の第2章
2012年10月3日
昨日読み始めた「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」 (貞友義典著・光文社新書)の続きです。
第2章も冒頭からものすごい勢いです。まずは運転免許と医師免許を対比させることからはじまります。
運転行為は、事故が起きれば自分も危険にさらされるので運転者も注意するが、医療行為はそうではない、だからこそ医療行為の方がより重い責任を科すべきだそうです。なるほどとも思われますが、では法律家のミスによる人権侵害についてはどうなんでしょう。重い責任を科されているでしょうか。
「医師を甘やかす医賠責保険」(医療賠償責任保険)という小見出しの項では、「医師が自腹を切ることはまだまだ少ないと言っていいでしょう」などとして、賠償責任を負っても自腹を切らないで済むことを問題視しているようです。しかもその同じ項では、高額の保険に加入することは被害者救済のために必要だとも述べており、結局何が言いたいのかよくわかりません。某県医師会長が、「保険料が1日当り63円で、居酒屋の焼き鳥1本より安いので加入すべき」旨を述べたことまで取り上げていますが、はっきり言ってどうでもいいことで、むしろ焼き鳥と対比をさせるという医師の庶民感覚を汲み取ってもらいたいものです(笑)。
賠償金についてはさらに続きます。ある産科の事件で医師が責任を認めて全額自腹で払ったことがあったそうなのですが、その医師は賠償金を用意するために、不動産を担保に借り入れたというのです。示談が終わり夫妻の家を出た医師に対して、激励をいい忘れたと家を飛び出す夫を筆者が見て、胸がこみ上げてきたというのですが、そのこみ上げてくるものを得た源泉に、不動産を担保に借金をした医師がいたことにどれほど心を致したか、気になります。これが美談なのであれば(確かに美談ですが)、悪意のない交通事故で過失責任を負ったら、全財産を投げ売って賠償することも美談だということなのでしょう。なんだかなぁ、と思います。
さて、裁判になった場合、法律家以外の方はご存じないかも知れませんが、担当医が法廷に出かける必要があるのは、通常は尋問を受ける当日の1回だけです。それは法律家から見れば当然のことなのですが、筆者はどういうわけかこれを問題視しているようなのです。さらに、「どうして被害者や遺族が証言をするときにそれを法廷で聞いてくれないのか」とも書かれています。それを聞かずに帰ることを問題視して、「被告医師は自分の尋問が終わればさっさと帰ります。なぜ、さっさと、そして場合によってはこそこそと帰ってしまうのでしょうか。」などと書いて、終了後の行動にまでケチをつけているのです。そういう一方でその直後には、医師が自分の尋問が終わった後にも帰らずに、「ふてぶてしく笑いながら原告本人の尋問を聞いているのも困ったもの」と述べており、ここでも何が言いたいのかよくわからないのです。ちなみに私がこれまでに傍聴した事件の中には、どう聞いても原告側の言いがかりであり、その通りに原告敗訴となっている事例が多々あります。特にそういう類の事件の場合は、筆者が問題視するような行動を訴えられた医師が取ることがむしろ当然と言えるでしょう。そういう事例も多々あるのです。
ちなみに、裁判官が明らかな誤りを犯したこと(例えば一宮身体拘束裁判のような)に対して無理を承知で提訴をしたら、その訴えられた裁判官はどうなるでしょうか。裁判の第一回目は訴えられた側は欠席が許されているため、「責任がない」旨を記した定型的な書面を提出します。そしてその提出によってその裁判の審理は終了し、次回は判決となります。しかし判決の日は訴えた側も訴えられた側も出席する必要がないので、訴えられた裁判官は欠席して終了、もちろん勝訴するのです。
ミスを繰り返しても医療賠償責任保険料の増額がないことも問題だと言います。確かにこの点は一考の余地があるかも知れません。しかしこの点はよく検討しないと、不成功に終わりやすい難症例でも、失敗したら保険料が上がるので手を出さないという医師が増えるかも知れず、却って社会の不利益に繋がる可能性もあるでしょう。ともあれそのような難しいことはさておき、『なぜこんなに甘やかすのでしょうか。なぜこんなに特別扱いをするのでしょうか。こんなに甘やかしていれば、「ミスをしても痛くも痒くもない。どうせ保険会社が全部やってくれる」と考えるだけで、反省などありません。』などと断定するのは如何なものでしょうかと言いたいです。
医師免許は取消されることがほとんどないことも問題視しているようです。しかしこれなどは、法曹資格の取り消しについてはどうかを考えれば、「おまえが言うな」の極致でしょう。「これらの実情を知るにつれて、このままでは医療ミス自体を減らすことはできないし、ミスを繰り返すリピーター医師もまたどんどん増えるに違いない、という確信に近いものを感じるようになりました。」といいます。そうであれば、弁護士についてもいろいろと甘いところがあるので、ミスとまでは言わずとも、問題弁護をする弁護士は増えていくように想像していますがいかがでしょうか。
ミスを犯した医師に、再研修制度がないことも問題だと言います。医師免許の更新制度がないことについては触れられているだけでしたが、筆者は他所で意見を述べられているようです。確かにこれらについては検討を要するものだと思います。法曹資格にも再研修制度と更新制度がないことを考えれば、なおさらそのように思います。
他にも細かいことがいろいろと書かれています。医師が原因不明と説明することが多いことについて、『世の中に「やることはきちんとやったが原因不明」なことがそんなにたくさん起きるとは思えません』などと述べていますが、これなどは私に言わせれば医学を甘く見ているのではないかと疑わせる発言であり、「あなたは医学に対してもそのような前提で、医療訴訟を受任しているのか」とひとこと言いたくなります。
「大きなミスを犯したら、もう医師としてやっていけない、というくらいの緊張感がないと、不勉強な医師はいつまでたっても不勉強なままです。」とも書かれています。私も、不勉強な患者側弁護士に緊張感を与えられるよう、より一層、無限大の厳しさで法廷を見つめていこうと、この本を読んで決意を新たにする次第です。
ちなみにここまで読んでも、まだこの本の半分に達していません(笑)

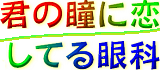
コメント
医師免許と運転免許を対比するのは私もどうかとは思います。しかし、私は一般人ですが、アメリカなどと比べて、日本の取消制度は甘いのではないかと感じます。この点に関してはやはり弁護士等の法律家よりも甘いという感じは一般庶民からは受けます。それから、今まで医師が足りないということが以前にわかっていたにもかかわらず、なぜ増やしてこなかったのかという疑問も厚生省や医師会に対して根強くあると思います。少なくとも一般庶民や一部の法律家よりも何倍から何十倍もの給与をもらっているわけですから責任をとる立場にあるのはある程度当然なのではないでしょうか?一般庶民からは病院を経営するお金持ちが自分たちの利益を守るために都合のよくないことを今まで直してこなかった、という感がぬぐえません。
しかし、本当にがんばっておられる勤務医の方や被災地で診療されておられる先生の環境を少しでもよくしてあげたいですね。
2012年10月17日 | EFF