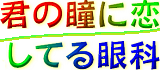令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
カテゴリー「医療訴訟」の記事
北見赤十字病院抗精神病薬投与死亡訴訟、控訴審第一回弁論
2013年4月15日
原告敗訴となった北見赤十字病院抗精神病薬投与死亡訴訟。一審では原告側から自称「キチガイ医」こと内海聡医師と清水宗夫医師の意見書が提出され(尤も、清水医師の意見書は裁判所はあまり取り上げていなかった模様)、尋問にも内海医師が登場し、自分では信念があって語っているようでありながら、因果関係認定には有効でない証言をしていたようです。
そんな事件ですが記録を閲覧したところ、控訴審にあたって控訴人らは、新たに仲田洋美医師の意見書を提出し、そこで指摘された新たな主張(腸閉塞、肺炎を見逃し、その結果敗血症を発症した、等)を展開。被控訴人の答弁書では、そもそも時機に遅れた攻撃であり却下を求めるとしながらも、ひと通りの反論をしている状況でした(摘便で排便しており、腸閉塞とは言えない、等)。ついでに言うと、仲田医師の意見書には、「他科依頼の返書を初期研修医に書かせるのは言語道断」とか、「精神科主治医が3年3ヶ月目の後期研修医で未熟な医師」とか、表面的な意見が沢山見られました。この診療過程を見て、腸閉塞とか言い出す仲田医師の診断のほうが過誤ではないかと思ったのですが・・・
そんな事件が控訴審に入ったわけですが、係属がなんとあの加藤新太郎裁判長の民事第22部。本日その控訴審第一回弁論が開かれました。腸閉塞や肺炎などの新主張の証拠となるCTやレントゲン画像が、提訴前に控訴人側(原告側)になかったのかを裁判長が控訴人代理人の望月宣武弁護士に尋ねると、あったというのです。そこから、加藤新太郎裁判長の追求です。「なんで原審で言わなかったの?」「原審では18回も弁論準備をしている。乾いた雑巾を絞り込むほどやっている」などと突っ込み、果ては「訴訟代理人の無能を救うわけにはいかないが・・・」とまで言うのです。
ではその新主張は直ちに却下かというとそうはいかず、病院側代理人の門間晟弁護士に対しても、「医療側の戦いも気になる。死因は不明ということでしょう。死因は不明、というのは、一般にはトボケている、ってことになりますよ」「一審では、心電図を取らなかった過失があるとなった。しかし死因は不明、ここが気持ちが悪い。」と。まあねぇ、医学の素人から見れば、「原因不明」ってのは、歯がゆいかとは思うんですけど、人間なんて所詮は動物の一種であり、医療なんて未知のことだらけなわけで、原因がよくわからずに亡くなるなんてことはよくあることなんですけどね。
まあ最終的には、腸閉塞や肺炎に対して病院側がそれなりに反論していた甲斐もあってか、合議の上で新主張は却下し、結審するということになったのですが、過失はあったが原因不明の死ということからか、和解を提案するという流れになりました。精神科には疎い私ですが、心電図などを取らなかったことが過失と判断されたことにも疑問を持つ私としては、如何なものかと思うんですけどね。
普通だったらものの数分で終わる控訴審第一回弁論が、今日はなんと30分を超過。まあ加藤新太郎裁判長の法廷を一度でも傍聴したことがある人なら、その厳しさも含めて何とも思わないことですが、一緒に傍聴していた弁護士さん(加藤新太郎裁判長の訴訟指揮初傍聴)は震えあがっていたけど、医者が医療事故で患者・遺族から責められるのよりは全然大したことないと思います。よく見ていると、代理人が裁判長から尋問を受けているようにも見えますね、というかそれそのものでしたね。
(平成25年9月29日、専門用語である「イレウス」を、「腸閉塞」に置き換えました。)
東京高裁民事部の開廷表の仕様が変わった件
2013年3月15日
今日、東京高裁地裁に出かけたら、東京高裁民事部の開廷表が、東京地裁民事部と同一のフォーマット(全国でも使われている)のものに変わっていた。
東京地裁民事部のフォーマットなので、「当事者(原告等・被告等)」との見出しがあり、「原:甲野太郎、被:乙山花子」のように、略称が付されている。しかるに東京高裁であるから、当事者はほとんどの裁判では原告、被告ではなく、控訴人、被控訴人である。
これに対して、東京高裁民事第2,4,12,15,23部では、特段の対策を取らなかった。
1,7部では、略称表記を削除した(1部はコロンも削除。)。
11部では略称表記及び見出しの「(原告等・被告等)」の表記を削除した。
13部では見出しの(原告等・被告等)の表記を削除し、略称の「原」を、手書きで「控」に書き換えた(「被」はそのまま。)。
5部では、開廷表はそのままで、末尾に「原告とあるを控訴人、被告とあるを被控訴人と読み替える。」と、大きい字で波線の下線を付して表記した。
対策を施した各部の対策は、それぞれ妥当と考えるが、私の考えでは、「(原告等・被告等)」については、「等」によって原告・被告に限られないことになるので、削除は不要であり、略称表記の「原」は、注釈を付けずに放置することには妥当性がないと思う。
裁判官が判決を間違えて、検察が控訴した模様
2013年3月10日
なにやら、神戸地裁で、裁判官が判決の出し方を間違えたために、検察が控訴したという事件があったようです。2013年3月10日 読売新聞より。
「少年は不定期刑に」地検控訴…裁判官勘違い?
強制わいせつ罪に問われた少年(19)に懲役1年10月の定期刑を言い渡した神戸地裁の判決があり、神戸地検が「少年法に基づいて刑期に幅を持たせる不定期刑が適用されるべきで判決は違法」として大阪高裁に控訴していたことがわかった。5日付。
関係者によると、少年は神戸市垂水区で昨年6月、女児に下半身を触らせたとして強制わいせつ罪で起訴された。
少年法では「少年に対して3年以上の懲役または禁錮をもって処断すべきときは、長期と短期を定めて言い渡す」などと規定。地検はこの規定が、法定刑を基に再犯や未遂といった事情を加味して決める「処断刑」の上限が3年以上の場合を指すとし、同罪の法定刑の上限が10年で減刑される事情もないため、今回の事件では懲役2年6月以上3年6月以下の不定期刑を求刑していた。しかし、地裁は2月21日、懲役1年10月を言い渡した。判決後に訂正の申し立てはなく、地検が協議後、控訴を決めた。
丸山雅夫・南山大法科大学院教授(刑事法)は「少年法の規定は検察と同様に解釈するのが通常。裁判官は『3年以上の懲役または禁錮を言い渡すべきとき』と規定を勘違いし、定期刑を言い渡したのではないか」と指摘する。
ツイッターなどで他の法律家の方々の反応を見ても、地裁判決は間違っているようです。奥村徹弁護士は「いやー誰にでも間違いがあるものですよ」と述べられています。私もそう思います。ところで、その「いやー誰にでも間違いがあるものですよ」が、業務上過失致死傷となると、犯罪として刑罰に付されることがあります。私にとって最も印象深い事件は、単なる言い間違いを犯罪として処罰され、結果として失職までさせられた日航機ニアミス事故ですが、一瞬のミスが犯罪とされる事例は、枚挙に暇がありません。それに対して判決の出し方を間違えるなどというのは、考慮時間は十分にあるのですから、過失の程度は一瞬の言い間違よりも重いのは明らかですし、また誤判という結果も、法治国家においては致死傷に負けず劣らず重大なのですから、業務上過失致死傷と同様に、「業務上過失誤判」とでも銘打って、犯罪行為として処罰したらどうでしょう? さぞかし誤判が減ると思いますよ。
なお、奥村徹弁護士によると、一部1係だということですが、裁判所サイトによれば、神戸地裁第一刑事部1係の担当裁判官は小林礼子裁判官だということになっていますが、合っているでしょうか?
泉徳治元最高裁判事が、最高裁裁判官国民審査制度に否定的見解
2013年2月20日
法学セミナーという雑誌の2013年3月号。巻頭言として、泉徳治*元最高裁判事の「最高裁裁判官国民審査制度は存続すべきか」という記事が掲載された。
氏の見解のもっとも重要な部分は、「裁判官は、国民の多数派が反対しても、個人、特に少数派に属する人たちの憲法で保障された人権を守るという役割を担っている。「yes」か「no」の投票で、任命の可否を決することはふさわしくない。」という部分だと思う。そして素人の私も、まさにそのとおりだと思う。
しかしながら、大橋弘トンデモ訴訟指揮事件での上告審のように、最高裁であっても、基本姿勢を誤った審理をすることがあるらしいことを見てしまった私としては、いくら最高裁とはいえ最高裁というだけで全幅の信頼をおけるものとは言えず、まずありえないとはいえ、万が一の場合に発動可能な安全弁があることは、無駄のようには見えても、一応の意味があるのではないかと思った次第。
氏が「我が国が「×」記号の記載のみを求める方式を採用したことは、賢明な選択であった」と評するように、このあたりが現実的な落としどころということで、良いのではないだろうか。正直、この件についてはそっとしておくのがいいように思うばかりである。
*正しくは「泉德治」(「徳」が旧字体)
「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」の第6章からあとがきまで
2012年10月26日
「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」 (貞友義典著・光文社新書)の読後感想文、ようやく最終回です。第6章は『リピーター医師、「国家賠償訴訟」へ』です。お産に関して同じミスを繰り返していたある産婦人科医について、厚生労働省が医業停止や免許取り消しなどの対策を取らずに放置していた責任を問うため、国を訴えたという事件の紹介がされています。
その産婦人科医の診療行為は実際に問題があったようですし、それが繰り返されたことに憤る気持ちは理解できるのですが、その槍玉に挙げられた医師は、問題になった事件の翌日から分娩業務をやめて、後遺症の治療費や入院費も全部持つと告げ、新聞記事になった際には取材に対して責任を認め、反省もしているということであり、それを超えて国を裁判で追求することには違和感を覚えます。
提訴にあたっては、毎日新聞の記者と打ち合わせをして、平成15年元旦の一面に記事を掲載してもらったそうです。事件番号についても、平成15年の第1号(津地方裁判所四日市支部平成15年(ワ)第1号)を取ったという気合の入れようです。その第1号を取るために用いた方法なんですが、四日市支部には元日は宿直も当直もおらず、訴状を直接届けることができないため、宅配便で元旦の時間指定便で四日市支部に送付したというのです。宿直も当直もいないことがわかっているにもかかかわらず、時間指定で宅配便を送るなどということは、私の考えでは宅配業者に無駄足を強いる迷惑行為だと思うのですが、そういうことを堂々と書くその見識を疑います。そもそも自動車のナンバープレートでもあるまいし、第1号を取ることにそこまで執心する意味もわかりません。
ちょっと脱線になりますが、この章で医療裁判の提訴についての筆者の見解が述べられているので見てみます。『私は提訴までにしっかり準備をしなくてはならないと考えています。(・・・) 裁判は医療裁判に限らず、最初が肝心です。特に医療裁判では「被告医師や被告病院の反論をみてこちらの主張を完成させる」とか「鑑定での意見を参考にこちらの主張を完成させる」などという方針はとんでもない間違いです。』と述べられています。してみると、訴状提出から主張が形になるまでに半年以上かかったこの事件などは、私も如何なものかと思っていたところですが、筆者から見ても「とんでもない事例」に映ると考えて差し支えなさそうです。これまでにもご紹介した沖縄地裁の総胆管結石の事例などは、主張が整理されるまでに提訴から3年以上です。しかもこの沖縄の事例などは結構な勝ち方をしているのですが、こんなやり方でもペナルティがあるどころか勝つ場合もあることは、羨ましい限りです。
さて、本題に戻って、リピーター医師提訴の内容そのものを確認したいと思います。私の理解では以下のようです。
1) 国(厚生労働省)は、医師・歯科医師に対して医業停止や免許取り消しを行う権限を持っている。
2) リピーター医師の存在は、平成7年に既に厚生労働省が把握することができていた。
3) それなのに、国はそのような医師を放置し、医療事故を招来した。
なるほど言われることは一理あり、医師や厚労省が考え直すべき部分もあると思います。一方、国はこの主張に対して、医療の質・内容を保証するものは、医師の自己研鑚であり、国の介入は最小限に留めるべきであると主張しているようです。高度な専門技術である医療の質については、現場で働く医師たちの自己研鑚に任せるしかないというのも、その高度の専門技術を評価できるのは医師以外にいないことを考えれば、ある意味止むを得ないことのようにも思われます。それに対して筆者は、それでも「国以外に私達の医療の質を保証するところはない」のであるから、国が積極的に介入すべきだと主張しているようです。
これは非常に難しい問題であり、どちらが良いかの検討は今は控えますが、裁判官・弁護士との対比はしておきたいと思います。まず裁判官ですが、裁判官は任期中は手厚く保護されている上に、10年の任期が満了しても、かつてはほとんど自動的に再任される仕組みだったようです。ところが最近では、相当に問題がある裁判官であると再任されない場合がちらほら出ているということなので(参考)、ある意味医師よりも厳しい面が出てきていると考えることができるかも知れません。ただし、再任されなくても、弁護士に転身することはできるのであり、何の資格もなくなるのではないということを付け加えておきます。
一方弁護士はというと、なんと弁護士には監督省庁がないというのです。厚生労働省は、医師・歯科医師に対して医業停止などの処分をすることができますが、法務省は、弁護士に対して弁護士業停止などの処分はできないのです。弁護士に対する処分は弁護士会が行うもの、つまり身内による処分があるのみなのです。そして弁護士の知り合いの方々から、「弁護士会の処分は甘い」という話をたびたび聞くことがあるくらいなので、あまり医師の処分が甘いとか言えたものではないのではないかという気がします。また、弁護士の質・内容を保証するものが、弁護士の自己研鑚しかない点も医師と同様なのですが、「そんなのでは保証にならない」などと言われたら、弁護士の方々はどう答えるのでしょうかね。
第7章は「リピーター医師から身を守るために」として、リピーター医師を忌避して良い医師を探す方法がアドバイスされていますが、こうすれば絶対という方法はないとも述べられています。これまた弁護士についても、問題弁護士を避けて良い弁護士を探すのが容易でないことと同じだろうと思いました。
あとがきには、筆者が尊敬する産婦人科の協力医である、我妻堯医師に本書を読んで頂いたエピソードが書かれています。それによると、『一気に読まれて、すぐに「よくできているよ」とのお言葉』をもらったというのですが、どこをどう読んだらすぐに「よくできている」と言えるのか、我妻先生に尋ねてみたい気持ちになりました。
「リピーター医師、なぜミスを繰り返すのか?」の読後感想文は以上です。長文にお付き合い頂きましてありがとうございました。
(後日注:「リピーター弁護士 なぜムリを繰り返すのか?」をアップしました。)