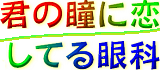令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」の第6章からあとがきまで
2012年10月26日
「リピーター医師 なぜミスを繰り返すのか?」 (貞友義典著・光文社新書)の読後感想文、ようやく最終回です。第6章は『リピーター医師、「国家賠償訴訟」へ』です。お産に関して同じミスを繰り返していたある産婦人科医について、厚生労働省が医業停止や免許取り消しなどの対策を取らずに放置していた責任を問うため、国を訴えたという事件の紹介がされています。
その産婦人科医の診療行為は実際に問題があったようですし、それが繰り返されたことに憤る気持ちは理解できるのですが、その槍玉に挙げられた医師は、問題になった事件の翌日から分娩業務をやめて、後遺症の治療費や入院費も全部持つと告げ、新聞記事になった際には取材に対して責任を認め、反省もしているということであり、それを超えて国を裁判で追求することには違和感を覚えます。
提訴にあたっては、毎日新聞の記者と打ち合わせをして、平成15年元旦の一面に記事を掲載してもらったそうです。事件番号についても、平成15年の第1号(津地方裁判所四日市支部平成15年(ワ)第1号)を取ったという気合の入れようです。その第1号を取るために用いた方法なんですが、四日市支部には元日は宿直も当直もおらず、訴状を直接届けることができないため、宅配便で元旦の時間指定便で四日市支部に送付したというのです。宿直も当直もいないことがわかっているにもかかかわらず、時間指定で宅配便を送るなどということは、私の考えでは宅配業者に無駄足を強いる迷惑行為だと思うのですが、そういうことを堂々と書くその見識を疑います。そもそも自動車のナンバープレートでもあるまいし、第1号を取ることにそこまで執心する意味もわかりません。
ちょっと脱線になりますが、この章で医療裁判の提訴についての筆者の見解が述べられているので見てみます。『私は提訴までにしっかり準備をしなくてはならないと考えています。(・・・) 裁判は医療裁判に限らず、最初が肝心です。特に医療裁判では「被告医師や被告病院の反論をみてこちらの主張を完成させる」とか「鑑定での意見を参考にこちらの主張を完成させる」などという方針はとんでもない間違いです。』と述べられています。してみると、訴状提出から主張が形になるまでに半年以上かかったこの事件などは、私も如何なものかと思っていたところですが、筆者から見ても「とんでもない事例」に映ると考えて差し支えなさそうです。これまでにもご紹介した沖縄地裁の総胆管結石の事例などは、主張が整理されるまでに提訴から3年以上です。しかもこの沖縄の事例などは結構な勝ち方をしているのですが、こんなやり方でもペナルティがあるどころか勝つ場合もあることは、羨ましい限りです。
さて、本題に戻って、リピーター医師提訴の内容そのものを確認したいと思います。私の理解では以下のようです。
1) 国(厚生労働省)は、医師・歯科医師に対して医業停止や免許取り消しを行う権限を持っている。
2) リピーター医師の存在は、平成7年に既に厚生労働省が把握することができていた。
3) それなのに、国はそのような医師を放置し、医療事故を招来した。
なるほど言われることは一理あり、医師や厚労省が考え直すべき部分もあると思います。一方、国はこの主張に対して、医療の質・内容を保証するものは、医師の自己研鑚であり、国の介入は最小限に留めるべきであると主張しているようです。高度な専門技術である医療の質については、現場で働く医師たちの自己研鑚に任せるしかないというのも、その高度の専門技術を評価できるのは医師以外にいないことを考えれば、ある意味止むを得ないことのようにも思われます。それに対して筆者は、それでも「国以外に私達の医療の質を保証するところはない」のであるから、国が積極的に介入すべきだと主張しているようです。
これは非常に難しい問題であり、どちらが良いかの検討は今は控えますが、裁判官・弁護士との対比はしておきたいと思います。まず裁判官ですが、裁判官は任期中は手厚く保護されている上に、10年の任期が満了しても、かつてはほとんど自動的に再任される仕組みだったようです。ところが最近では、相当に問題がある裁判官であると再任されない場合がちらほら出ているということなので(参考)、ある意味医師よりも厳しい面が出てきていると考えることができるかも知れません。ただし、再任されなくても、弁護士に転身することはできるのであり、何の資格もなくなるのではないということを付け加えておきます。
一方弁護士はというと、なんと弁護士には監督省庁がないというのです。厚生労働省は、医師・歯科医師に対して医業停止などの処分をすることができますが、法務省は、弁護士に対して弁護士業停止などの処分はできないのです。弁護士に対する処分は弁護士会が行うもの、つまり身内による処分があるのみなのです。そして弁護士の知り合いの方々から、「弁護士会の処分は甘い」という話をたびたび聞くことがあるくらいなので、あまり医師の処分が甘いとか言えたものではないのではないかという気がします。また、弁護士の質・内容を保証するものが、弁護士の自己研鑚しかない点も医師と同様なのですが、「そんなのでは保証にならない」などと言われたら、弁護士の方々はどう答えるのでしょうかね。
第7章は「リピーター医師から身を守るために」として、リピーター医師を忌避して良い医師を探す方法がアドバイスされていますが、こうすれば絶対という方法はないとも述べられています。これまた弁護士についても、問題弁護士を避けて良い弁護士を探すのが容易でないことと同じだろうと思いました。
あとがきには、筆者が尊敬する産婦人科の協力医である、我妻堯医師に本書を読んで頂いたエピソードが書かれています。それによると、『一気に読まれて、すぐに「よくできているよ」とのお言葉』をもらったというのですが、どこをどう読んだらすぐに「よくできている」と言えるのか、我妻先生に尋ねてみたい気持ちになりました。
「リピーター医師、なぜミスを繰り返すのか?」の読後感想文は以上です。長文にお付き合い頂きましてありがとうございました。
(後日注:「リピーター弁護士 なぜムリを繰り返すのか?」をアップしました。)