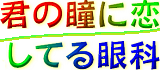令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
カテゴリー「医療訴訟」の記事
西島幸夫裁判官の過去の判決
2012年3月6日
いくらなんでもありえないと言っても過言ではない、一宮身体拘束訴訟の控訴審の裁判長であった西島幸夫判事が以前に出した、疑問符の付く判決の報道を見つけたので、備忘録として記しておきます。
毎日新聞 <医療ミス訴訟>中津川市に1億3千万円余賠償命令 控訴審
ヘルペス脳炎で重度の後遺症を負ったのは中津川市民病院(岐阜県中津川市)の医師の診断ミスだとして、同市内の男性(46)が市に2億2100万円の損害賠償(その後、1億6500万円に請求額を変更)を求めた訴訟の控訴審判決が9日、名古屋高裁であった。西島幸夫裁判長は約1億3100万円の支払いを命じた1審名古屋地裁判決をほぼ支持。市側の控訴を棄却し、慰謝料などを上乗せした1億3400万円の支払いを命じた。
1審判決は、医師が男性のヘルペス脳炎を精神疾患と判断したことについて「脳炎の十分な検査をしていれば重度の後遺症を避けられた可能性が高い」と過失を認定。これに対し、市側は、患者や家族が記入する問診票に頭痛の症状の指摘がなかった点などを主張し、「当時の状況でヘルペス脳炎と判断するのは難しかった」と争っていた。【式守克史】
筍ENTのブログから拝借しました。そちらの解説も併せてご覧ください。
裁判での医療行為の適否判断の困難について
2012年3月5日
2006年に福島で産婦人科医が逮捕された、大野病院事件に関する古い書き込みです。
——————–
もしこの大野事件の医療行為をカンファレンスや学会シンポジウムなどで検討すれば、それこそ事実解明は十数分~数時間程度で完結する簡単なものでしょう。この裁判における田中教授の意見はおかしなものなのでしょうが、これがもしカンファや学会だったら、皆からオイオイと言われてあっさり却下されて終了でしょう。アホに見える意見書でも、医療者内で適切に処理すれば害になることはまずないはずです。
ところがそんな簡単な結論を出すのに、裁判っていうものは、何年もかけて、忙しいはずの各大学の教授陣など大勢を巻き込んで、オカシな意見でもさも真っ当な意見のように偽 装され、普通に真面目な医師の名誉を毀損して、時に医学的に全くオカシな判決を出して、そして…医療を崩壊に走らせて。
刑事だろうが民事だろうが、こんなシステムでやってたら医療は当然に崩壊する、ということを法曹(司法、検察、弁護士)に粘り強く語り続けなければいけないと思います。
——
証人が普通の人であっても、いざ証言台に立てば順当な証言ができるか否かは、証人によって違ってきてしまうだろうと危惧します。
医学・医療的な問題に関しては、より迅速に真実に近づくためにはやはり多人数の医師が検討する必要が絶対に必要だと思います。
いっそのこと、学会で訴訟案件検討のセッションを設けて討議してみてはどうかと思います。勝手に被告側で企画・実行して、結果を証拠なり陳述書として提出してみることくらいはできるでしょうし、それなりにインパクトがあるのではないでしょうか。
神戸大抗がん剤投与死亡訴訟で和解1500万円
2012年3月4日
NHKオンラインのキャッシュからですが、
抗がん剤投与死亡訴訟 和解
神戸大学の付属病院で抗がん剤の投与を受けた12歳の男の子が死亡したことをめぐり、遺族が医療ミスだと訴えた裁判で、病院側が解決金として1500万円を支払うことで和解が成立しました。
この裁判は11年前、神戸大学医学部付属病院で、当時12歳の男の子が悪性リンパ腫の治療中に死亡したことについて、母親が「抗がん剤の副作用が原因で治療を過った」と訴え、病院側に賠償を求めていたものです。
1審は、母親の訴えを退けましたが、2審の大阪高等裁判所が去年12月、「医師が男の子の状態を十分に確認しないまま、抗がん剤の投与を続けた過失がある」と指摘し和解を勧告していました。
これを受けて協議が進められた結果、病院側が母親に1500万円の解決金を支払うことできょう和解が成立しました。
母親は、「医療現場では抗がん剤の投与を適切に行い、このような事故を2度と起こさないでほしい」と話していました。
一方、神戸大学医学部付属病院は「医療ミスとは認識していないが、裁判の長期化などを考えて和解に応じた」としています。
03月01日 18時46分
この記事からは、どんな過失があって、死亡との因果関係があるのか皆目見当不明です。他の記事によれば、一審神戸地裁判決は「専門医の研究会が作った手順に従っていた」として請求を棄却したものを、大阪高裁で西村則夫裁判長が過失があると判断したようですが、一審では専門医の研究会が作った手順に従っていたと認定したものを、どのような思考回路で過失ありの指摘をしたのかは大変興味深いところです。
そして、一審で過失を否定され、また大学側も医療ミスと認識していない事故に対して、1500万円もの和解金で手を打つという感覚が、さらにわかりません。
別件ですが、最近、苫小牧市立病院から麻酔科医が消えるというニュースがありました。この記事の中に、
一昨年、苫小牧市立で起きた医療事故の対応をめぐり、医師と病院側の信頼関係にひびが入り「そういう対応の病院では勤務できない、という医師もいる」(山蔭教授)。
という一文があります。その、元となった事件である可能性があるニュースがあり、これであったという確証はありませんが、このような対応をする病院には勤務できない、という感想を医師が持つ心情はなんとなくわかる気がします。
医療の最高機関とも言える大学病院が医療側の主張を通しきらずに、周辺事情によって高額の和解を選択したことは、大変残念ですし、苫小牧市立病院と同様な事態を引き起こす原因の一つになりはしないかと、人ごとながら心配します。
医療事故調査委員会の議論再開
2012年3月1日
たなざらしになっていた、医療事故調査委員会の検討が再開されるようです。
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36616.html
座長が法学研究科教授なんですね(山本和彦・一橋大学大学院)
私は医療裁判を見るようになってから、裁判官や弁護士にも、医師に負けず劣らずお粗末事例が多いことを知りました。ところが法律家の仲間内のかばい合いたるや、医師の比ではないのです。例えば判決文に明々白々な矛盾があっても、法律雑誌では一切触れられないのです。 例:一宮身体拘束訴訟→ http://www.minemura.org/iryosaiban/H20ju2029.html
事故調のニュースからの引用ですが、元々患者側で活躍されていた弁護士である加藤良夫教授は、
ここに参加している委員で一致しているのではないか。事故が起きても、情報収集することなく、分析もされずに放置されたら、医療の質を向上させる文化は育っていかない
と言われているようなんですが、これは弁護士も同じでしょう。ただ、弁護士の場合、依頼人との関係でオブラートに包まれてしまうので、外部からはそれが弁護過誤だったのか、当事者の意向であるためやむを得ないものであったのかの判断はつきにくいですが。二代目センター長である柴田義朗弁護士が受任した眼科の事例では、微妙なものもありましたし(後日上梓予定)、身内についてはきちんと目を配っているのでしょうか。いっそのこと、司法事故調や弁護事故調を、医療事故長とセットで検討したらどうかと思います。
一般的な話ですが、自分に甘く、他人に厳しい人々というのは、私からすると最も軽蔑すべき人々であります。
別に司法事故調、弁護事故調をホントにやれというのではありませんが、そういう類のものをやることのメリットとデメリットを、法律家はよくよく推察するべきですね。
嘘つくんじゃないよ! 話したことないんだから!!
2012年2月22日
似たような題名の投稿が続きますが、本日傍聴した事件です。
歯科の治療がうまくいかなかったと主張して提訴したらしいのですが・・・
被告代理人が被告医院の歯科衛生士に対して、患者(原告)にどんな説明をしていたのかを尋問している途中、突然原告本人が、
「嘘つくんじゃないよ! 話したことないんだから!!」などと絶叫しだしました。
しかもこの事件、前回日記と違って原告代理人がついており、この絶叫は原告席ではなく、傍聴席で傍聴していた原告からなされたものでした。
これに対して被告代理人や裁判長から注意があるも、原告代理人は沈黙・・・
尋問再開してしばらくすると今度は、引き続き傍聴席に陣取る原告が、背筋を伸ばして挙手。「ちょっと・・・」
ここで裁判長、強い注意。「前にも言いましたが、傍聴席で発言したり・・・これ以上話したら退廷してもらいますよ」と。
再度尋問開始するも、またしばらくして挙手。「ちょっといいですか?!」
裁判長「ダメだと申し上げたはずです」
その後も、声をあげて笑ったり、携帯電話を鳴らしたり、ときには傍聴席の前の柵を握りしめて証人を見つめたりと、なかなかにすごい光景でした。それをまた原告代理人が注意もしないものだから、休廷時間に入るときに裁判長から、原告代理人に対して、原告本人に注意するように指示がありました。
しかし、この尋問で一番面白かったのは、被告関係者に対する被告代理人の質問に対して原告代理人が、
「異議あり! 誘導尋問じゃないですか?!」
というツッコミを入れた瞬間でした。
・・・
・・・
・・・
被告関係者に被告代理人が質問するんだから、被告に有利に質問するのが当たり前だろうが・・・
追記:
私の素人理解と違って、主尋問(味方側の尋問)での誘導尋問は、正当な理由がない限り違反であるとのご指摘を受けました。ただしこの異議が発せられたタイミングは、尋問の最初のほうの、被告側が主張する事実経過の確認段階のもので、わざわざ異議を挟むような場面ではなかったようにも思います。しかし私の素人理解が誤っていたことは明らかで、ここに追記をする次第です。