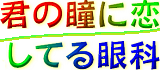令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
「ビタミンKを投与せず乳児死亡」
2010年7月10日
もう各所で話題になっている事件ですが、まとめがてら…
「ビタミンK与えず乳児死亡」母親が助産師提訴
生後2か月の女児が死亡したのは、出生後の投与が常識になっているビタミンKを与えなかったためビタミンK欠乏性出血症になったことが原因として、母親(33)が山口市の助産師(43)を相手取り、損害賠償請求訴訟を山口地裁に起こしていることがわかった。
助産師は、ビタミンKの代わりに「自然治癒力を促す」という錠剤を与えていた。錠剤は、助産師が所属する自然療法普及の団体が推奨するものだった。
母親らによると、女児は昨年8月3日に自宅で生まれた。母乳のみで育て、直後の健康状態に問題はなかったが生後約1か月頃に嘔吐(おうと)し、山口市の病院を受診したところ硬膜下血腫が見つかり、意識不明となった。入院した山口県宇部市の病院でビタミンK欠乏性出血症と診断され、10月16日に呼吸不全で死亡した。
新生児や乳児は血液凝固を補助するビタミンKを十分生成できないことがあるため、厚生労働省は出生直後と生後1週間、同1か月の計3回、ビタミンKを経口投与するよう指針で促している。特に母乳で育てる場合は発症の危険が高いため投与は必須としている。
しかし、母親によると、助産師は最初の2回、ビタミンKを投与せずに錠剤を与え、母親にこれを伝えていなかった。3回目の時に「ビタミンKの代わりに(錠剤を)飲ませる」と説明したという。
助産師が所属する団体は「自らの力で治癒に導く自然療法」をうたい、錠剤について「植物や鉱物などを希釈した液体を小さな砂糖の玉にしみこませたもの。適合すれば自然治癒力が揺り動かされ、体が良い方向へと向かう」と説明している。
日本助産師会(東京)によると、助産師は2009年10月に提出した女児死亡についての報告書でビタミンKを投与しなかったことを認めているという。同会は同年12月、助産師が所属する団体に「ビタミンKなどの代わりに錠剤投与を勧めないこと」などを口頭で申し入れた。ビタミンKについて、同会は「保護者の強い反対がない限り、当たり前の行為として投与している」としている。
(2010年7月9日 読売新聞)
助産師会が主催する講演会、セミナー、イベントについて調べたところ、ホメオパシーとの濃密な関係が浮き彫りになったのでご紹介する。
・日本助産師会和歌山支部主催の講演会
平成18年5月13日、日本助産師会和歌山支部主催の講演会で、日本ホメオパシー助産師協会会長の鴫原操が講演を行った。・日本助産師会大阪府支部主催の講演会
平成18年、日本ホメオパシー医学協会(JPHMA)会長の由井寅子が講演を行った。
平成19年にも由井寅子の講演が行われている。・日本助産師会東京都支部主催の講演会
平成19年、日本ホメオパシー医学協会(JPHMA)会長の由井寅子が講演を行った。・日本助産師会大分県支部研修会
平成20年11月3日、日本助産師会大分県支部研修会が行われた。イベント会場において、「ホメオパシーコーナー」が設けられた。・兵庫県助産師会主催によるホメオパシー講演会
平成20年3月19日、兵庫県助産師会主催による鴫原操、由井寅子両氏の講演会が行われた。・日本助産師会広島県支部による研修会(講演会?)
平成20年、「出産とホメオパシー」という研修会(講演会?)が行われた。
助産院は安全?の、
お子さんが亡くなってしまいました
ホメオパシー、レメディの問題>K2シロップの件
「ビタミンK与えず乳児死亡」母親が助産師提訴
その他、こちらのブログを「ホメオパシー」で検索すると、沢山の情報が得られます。(5つずつしか出てきませんが、「次のページ」を繰っていくと続きを見れます。)
今回の提訴は民事訴訟ですが、刑事事件になった場合には…
予見可能性…あり
予見義務…あり
結果回避可能性…あり
結果回避義務…あり
でしょうから、とりあえず公判を維持できる可能性は十分ありそうです。本来は、専門家の判断を厳しく追求することには慎重にすべきとい考えていますが、この件は刑事も有り、むしろそれが妥当かと思います。科学的に十分根拠のある最低水準の治療法を、非科学的な根拠をもって故意に排除した結果、死亡という結果を招いていますからねぇ…
「そもそも業務上過失致死罪の存在に反対」する私がこのように考えるのは、私の考え方にブレがあるからなのでしょうかね?
こういう受任はどうなんですか…
2010年7月4日
昨日の報告の続きで、記録を閲覧した結果です。
裁判長が「訴状では,個々の過失と死亡との因果関係を述べていないので,個々の過失とのつながりをもうちょっと述べて頂くと良い」と述べられていたわけですが、確かに過失はせっせと書いたのに、因果関係は全くガサツな書き方です。裁判長の言いたい気持ちも分かります。
が、それを置くとしても、この提訴はひどいでしょう・・・
この事件の原告、亡くなった方の婚約者とは言っているけれども、そもそも慰謝料請求権があるのでしょうか? あとから調べてみたところ、親族以外への慰謝料が認められることはそうそうないようなんですが、この事件のように、知りあってから15年も経過していながら結婚もせず、さらには同居しているわけでもなく、お金を借りるにあたって借用書を書き、婚約の証拠が牧師さんの陳述書だけで、遺族である母(亡き妹の相続人でもある)以外の者が慰謝料を求めて提訴するというのは一体なんなのかの疑問です。
そういえば去年、福岡地裁でもなんだかなあ、と思う事例を見ました。被告男性の子(加害者・未成年)が,原告の母(被害者)を自転車で跳ねたという事件で、その被害者の治療費を被告に請求しようと提起した事件でした。しかしそれは跳ねられた被害者(原告の母)が提訴するのが普通じゃないですか。さらに聴いていると、実は被告は離婚していて、加害者(被告の娘)の親権は被告ではなく母親が持っているそうなorz…
ま、そんな事件もあるのだから、今回の婚約者訴訟もアリかとは思わなくもないですが、でも福岡の事例は、本人訴訟だったんですよね。
閲覧メモはかなり要約になっています。
平成22年(ワ)第8189号
原告 X
原告代理人 森利明
被告 Y
被告代理人 小西貞行、Z1、Z2、Z3
訴状 平成22年3月4日
請求 3100万円+遅延損害金
1 当事者等 亡A 昭和29年○月○日生、平成18年9月11日自殺
ア AとXは実質的に配偶者と同視できる。以下の事情から。XはAと平成3年にお見合いし、15年間交際している。当時原告は43歳、Aは36歳で若くなく、結婚前提で交際を開始した。
イ 平成14年○月、原告が脳出血で倒れ、後遺症で右手足麻痺になった。AとXは共に生きていくことを相互に確認した。キリスト教信者であるAが、日本キリスト教団○○教会のD牧師に婚約していると話していた。(D牧師の陳述書あり)
ウ △△市に3LDKマンションを購入、生活を準備していた。
エ XがAの生活を支援していた。Aは家の1階を貸して家賃収入を得ていたが、店子が退去し収入が減少。その減少に見合うくらいの収入のある投資信託を見つけて、XがAに3300万円を援助して購入。借用書あるが担保、返済期限は無い。
オ 精神的に支えていた。
カ Aの姉Bも支援し、財産管理をしていた。
キ Aの死後には、Aの母Cを支援している。
ク Xは証拠保全を申立て、保全の決定がなされた。
ケ まとめ。
2 事案概要
AはYクリニックで平成3年4月6日から精神科治療を受けた。平成18年9月9日最後の受診、同月11日にとびおり自殺。Aの婚約者のXが、自殺はYの診断及び医薬品の副作用などにおける過失が原因と主張して、賠償を求める事案である。
3 経過
平成3年4月6日にYクリニックを初診。Y医師にはそれ以前に○○大学病院で受診していた。初診時から統合失調症と診断された。Yクリニックは院内処方。多数の投薬を受けていた。Aの姉Bは平成10年に大腸癌、その後肝転移した。平成18年8月22日にAは、Bが余命3ヶ月だと聞いた。平成18年9月9日にAはYクリニックを受診した。Yは「医者がそう言うんじゃそうじゃないの」などと言い、極めて冷淡でAの絶望感を誘うような応答をした。その2日後に自殺。
(峰村注:4が抜けているのは私のミスかどうか不明)
5 Yの過失
1)診断の過失
・YがAを診察した間、カルテには診察中に統合失調症症状を目撃・観察したとの記述はない。
・XはAと過ごした15年間に統合失調症症状を見ていない。
・Cも見ていない。
・Bも見ていない。
・社会的に、十分根拠のないまま安易に統合失調症と誤診され、投薬されて抑鬱が強くなる例は数多く、社会的に問題となっている。
2)投薬の過失(添付文書違反)
投薬一覧
・インプロメン 9~12mg 平成14年4月~平成18年7月
・コントミン 25~50mg 平成14年4月~平成16年1月(平成14年5月と、平成15年11月を除く)
・リントン 2.25~3mg 平成15年9月~平成18円9月
・タスモリン 平成14年4月~平成18年9月
・レキソタン 平成14年4月~平成18年9月
・ロヒプノール 平成14年4月~平成18年9月(平成14年5月を除く)
・ベゲタミンB 平成17年10月~平成18年9月
(原告が入手できた診療報酬明細書はこれだけ)
・統合失調症薬の同時投薬時にはクロルプロマジン換算で判断する。インプロメンは1gあたりクロルプロマジン換算で50mg、リントンも同様。コントミンはクロルプロマジンの製品名でありクロルプロマジンそのものである。クロルプロマジンの容量は添付文書上50~450mg。万一仮にAが統合失調症であったとしても、症状は明らかに軽微だったのだから、過剰投与が明らかである。特に平成18年8月から9月。
・ロヒプノールは2~4mg。文書上は0.5~2mgである。米国では禁止薬物。英NHSでは禁止薬物、ドイツでは1mg錠までしかない。
・薬物性肝炎の診断がされている。平成3年9月14日~平成15年迄に採血は3回。
GOT GPT γ-GTP
平成12年 61/71/92
平成15年 70/91/139
平成18年 60/50/136
・レキソタンは適応外。
3)投薬上の過失(医師法違反)
宅急便による医薬品の投与。少なくとも平成17年10月5日~平成18年9月6日までに7回。
カルテに診察記録がない。医師法20条1項に違反する。
4)薬の副作用に関する過失
・肝機能低下。抑鬱が出やすい。
・無診察処方。患者を問診し、直接よく観察することなく処方していた。
・カルテには、電話によるAの発言内容が多数記載されている。診察を電話にて済ませていたことが多かった。
・自殺に至る前の数カ月間の診療録は内容がほとんどない。診察した場合でもYの診察は超短時間(←原文ママ)のおざなり診療だった。
・Yが薬物依存性に無頓着だった。
5)うつ病を見逃し、うつ病対策を取らなかった過失。
6)自殺直前の診察における過失。(峰村注:先述の、冷淡な診察のこと)
6 過失と自殺との因果関係
5で述べた通り、Yには「診断上の過失」「投薬上の過失」「薬の副作用に関する過失」「うつ病を見逃し、うつ病対策を取らなかった過失」「自殺直前の診察における過失」
これらの過失により、もしくはこれらの過失が相まってAはうつ病になり、Yがうつ病対策を何ら講じることなくAは自殺したのであるから、因果関係は明らか。
7 損害額
慰謝料 3000万円
弁護士費用 100万円
—————–
提訴前に証拠保全が執行されたが、カルテ等は被告代理人のところにあったため、検証不能だった。後日原告側は、被告側から任意にカルテの提出を受けた。
甲号証にカルテなどが提出されているが、カルテは初診時分と最後の2ページだけで、途中が提出されていない。
裁判所から原告側への紹介には、「被告との事前交渉は無い」とされている。これは被告側が交渉を拒絶したということかな? (カルテをもらったのだから、そもそも原告側がコンタクトを取らなかったということはあり得ない)
—————–
第1回弁論調書らしきもの(裁判所が作成したもの)
裁判長:
1 甲A2号証の診療報酬明細書に黒塗りがあるが、原告が塗ったものか。
2 Aの死亡と個々の過失のつながりの主張を。
3 甲B1、甲B2(いずれも医学文献)は平成3年当時のものではないが、過失とのつながりを検討してもらいたい。
原告側:
1 甲A2は、最初から黒塗りされていた。(恐らく統合失調症の病名)
2 上記2,3について検討する。
3 書証の原本は次回持参する。
—————–
平成14年3月の、診療報酬明細書の記載
病名
〓〓〓〓〓 平成3年4月6日 (峰村注:黒塗り)
薬剤性肝炎 平成3年9月14日
慢性鼻炎 平成6年11月2日
胃潰瘍 平成11年11月6日
レセプトに「電話再診」の記載あり。
(平成22年7月6日、文意を分かりやすくするための軽微な修正)
顔を洗って出直して来い!
2010年7月3日
2010年4月22日のことです。東京地裁と東京高裁の第1回口頭弁論を傍聴してきました。
一つ目は東京地裁民事第14部,平成22年(ワ)第8189号。原告本人と代理人弁護士が出廷。
裁判長から原告代理人に対して「訴状では,個々の過失と死亡との因果関係を述べていないので,個々の過失とのつながりをもうちょっと述べて頂くと良い」旨の発言あり。
二つ目は東京高裁民事第21部,平成22年(ネ)第364号。開廷直前まで,原告側に弁護士らしき人がいないなぁ…と思っていたら,普段着の比較的若めの男性が登場。
本人訴訟だ…
裁判長「控訴理由書に,1, 2, 3, 4…と理由が述べられていて,7からは, 7, 8, 9, 10 とあるけれども何も書いてありませんが…」
原告「…思いつきませんでした」
裁判長「ではこれは削除ということで宜しいですか?」
原告「はい」
で,地裁で主張は尽くされているということで,裁判長は結審しようと思ったようですが,原告側から「後医の私的意見書を依頼している」との発言があり,弁論続行になりました。しかし私的意見書について,後医は匿名で書くという意向だったようで,その旨を原告が述べると裁判長から「それでは尋問もできないし」みたいなツッコミあり。
ここでふと思うことは,二つ目の「控訴理由を思いつかなかった」本人訴訟の控訴審と,「過失と死亡との因果関係を述べていない」代理人弁護士がついた東京地裁の訴訟とで,ダメさ加減にどれほどの差異があるのだろうか,と思ってしまったわけです。
(続く)
弘中惇一郎弁護士が訴えられた事件
2010年6月20日
控訴審の開廷表で見つけた事件で、弘中惇一郎弁護士が控訴し、さらに上告ないし上告受理申立てがなされていたことから気になっていた事件で、だいぶ前に千葉地裁で閲覧してきました。
同じ弘中惇一郎弁護士でも、以前に円錐角膜移植手術後散瞳症訴訟で見られたような、素人目にも明らかと思われる単なる弁護過誤事件と違い、今回の事件は素人目にはそれなりにややこしい事件で、この事件に先立って3件の提訴がありまして。
1.
商品先物取引の「Y株式会社」から損害を被ったとして、被害者XがY株式会社に対して7000万円あまりの賠償請求を提訴(一次訴訟)、1800万円支払いで和解し、期日指定された平成18年1月20日までに支払済み。その際のY株式会社の代理人が弘中氏ほか、Xの代理人がS弁護士。
2.
その5ヶ月後の平成18年6月1日、Xが、担当社員であったAなどに対して、被った損害の一部として1000万円の賠償請求を提訴(二次訴訟)(これはのちに600万円で和解)。その際のXの代理人がS弁護士、Aなどの代理人が弘中氏ほか。
3.既に一次訴訟で和解している上に、担当社員に対してさらに提訴した第2事件の提訴は信義則に反して違法だとして、平成18年9月16日、AなどがXおよびS弁護士に対して弁護士費用など160万円の請求を提訴(三次訴訟)(これはのちに棄却)。Aなどの代理人が弘中氏ほか。
以上の流れから、今度はS弁護士が弘中弁護士ほかを訴えたというのが、今回閲覧した事件でした。
争点は、(1)二次訴訟提起の不当性(Xは、一次訴訟の和解によってAらに対する請求を放棄していたか)、(2)三次訴訟の不当性、の二つでした。
地裁判決に示された事実
(1) 一次訴訟提起前、S弁護士が弘中弁護士に対してAの住所を開示請求した。弘中弁護士は守秘義務を理由として拒否。
(2) Xは一次訴訟の和解に応じたものの、金額と、一次訴訟にてAの尋問がなされなかったことから納得がいかず、Xは後日S弁護士に対して、Aらの責任追及を希望する旨を表明。
(3) S弁護士は、通常の会社であれば6~7割の和解が可能と考えていたため、Xを気の毒に感じていたものの、Aの資力に期待できないからとXに再考を促したが、Xは受け入れなかった。
(4) 一次訴訟の5ヵ月後、二次訴訟を提起。Aの住所については裁判所に調査を申し立てた。
一審の判断は、
(1) 一次訴訟では、XがAに対して債務免除の意思表示をしたとは認められず、二次訴訟の提起は正当である。一次訴訟で、Aを相手取らなかったのは、支払能力に疑問があったからであって、住所不定であったからではない。これは二次訴訟でAの住所を「Y内」として提起されていたことからわかる。
(2) 三次訴訟は不当である。
で、弘中氏らは50万円+弁護士費用10万円を支払うよう認めた。
控訴審の判断は大雑把に言ってしまえば、裁判所に判断を求める権利は憲法で保障されているものであり、三次訴訟は不当とは言えない。というもので、一審判決は破棄されました。
原告側は上告および上告受理申立てをしましたが、受理されませんでした。
なにやら弘中氏は、こちらに紹介されている例のように、他の弁護士から煙たがられる可能性のある訴訟の受任もしているようで、それを他の弁護士から煙たがられていたのかなぁ、と感じられました。S氏側に30人も代理人がついたのはその辺が理由だったんでしょうかね。今回閲覧した事例は、非法律家である私としては「どっちもどっち」という感想です。
医療訴訟の場合、医療関係者から見れば「これは濫訴だろう」と思われるような提訴が結構あるのですが、裁く人たちも素人なので、実際にはそういう例で逆提訴しても、濫訴とはなかなか認められないでしょうね。
一審の判断理由をもっとしっかり読んでこれたら良かったんですが、時間的に叶いませんでした。
千葉地裁平成18年(ワ)第2503号
東京高裁平成20年(ネ)第150号
平成20年(オ)第1068号
平成20年(受)第1295号
原告 S
原告代理人 大槻厚志 外30名 (←どの審級でのものか失念)
被告 弘中惇一郎、加城千波
(平成23年10月6日、弁護過誤リンク追記)
魅惑の三平方の定理医療訴訟
2010年6月13日
本年6月3日に、本人尋問を傍聴した事件です。
平成22年(ワ)第61号
原告席にはざっくばらんなおじさんが一人。
本人訴訟だ…
秋吉裁判長から、「弁論更新の手続をいたします。趣旨としては・・・」と、弁論更新手続きにまで説明を付けるサービス。それはさておき。
代理人弁護士がいないから、左陪席(ネーベン)が質問を開始。では、スタート。
(いつものことですが、明示した以外にも、途中結構抜けはありますがご了承を)
左陪席
被告から血管の穿刺を受けるようになったのはいつからか?
—— 3年以上経っています。A病院から別の病院に転院したのはいつ?
—— 昨年11月転院するまでに被告から受けた血管穿刺の問題点は?
—— 3つのポイントを上げて書面にまとめました。1、血管は細いくだで、血管を刺した注射針が反対面に突き当たり、血管痛を起こす。2、物理でいうテコの原理。穿刺針では把手が力点、穿刺口が支点、針の先端が作用点。入射角によって、高い角度で指すと、入れてすぐグイと下げないとならない。すると支点に力がかかる。透析患者は動脈圧が静脈に流れる。いつも怒張している。私は触って推測するに、血管内径は3mmあるいはそれより細い。支点による力、あとで直角三角形の定理を説明しますが、圧迫性血管痛を引き起こす。以上3点から・・・裁判長
ちょ、ちょっとよろしいですか、先ほど3点にまとめたとおっしゃられましたが、今のお話では2点しか話されなかったように思うのですが、
—— 1、血管の反対面に突き当たり血管痛を起こす、2、高い角度で刺入することによるテコの原理、3、1と2の複合による。3点目は1点目と2点目の複合ということですか
—— はい左陪席
針の角度は何度とすべきか?
—— 私の考えでは10度。しかし10度だと血管が逃げる。分度器などで図ると15度が相当。自分で計算した結果か?
—— はい。計算の理由を聞いてくれますか?理由は? (←左陪席優しい)
—— 直角三角形の定理というか、理想的な直角三角形を外れた場合は必ず・・・(途中不明)、三平方の定理だけが一般的な看護師・・・(途中不明)、加法の定理もあるが、これは難しいので必要ないと思う。穿刺をどこに受けたか
—— 左の前腕と上腕。入射角は何度くらいだったか?
—— 測ってやろうと思い、分度器をポケットに入れていって・・・結論を教えてください。
—— 60度を超していたと思う。根拠は?
—— 自分で測りました。(原告がえらく身を乗り出しているのを左陪席が見て) 聞こえにくいですか?
—— いや、聞こえるけれど、慎重に聞こうと思いまして。枕は必要ですか? (腕枕のこと)
—— 15度の場合は不要。丸太を想定した場合(・・・)、仮に30度で刺入したとしても、斜面によって(・・・)枕をあてがわないと無理が生じる。被告は枕を使ったか?
—— 私が求めて、枕を使ってもらいました。いつ頃のことか?
—— 被告が刺入するときは場所による。なるべく低い角度から刺してくれと常日頃から言っていた。だんだん角度が低くなっていったが、15度にはならなかった。被告代理人
甲A1号証、甲A2号証(陳述書)を作成する際に、医学文献は参照したか?
—— 医学文献は持っていません。参照していない?
—— していない。医学文献に近いものは図書館で見ました。それを写したということか?
—— いや、写してなんかいません。被告の刺入角度は、何度くらいまで低くなっていたか?
—— 30度を超していたと思う。最初は60度を超えていたと思う。60度を超えると、固定できないのではないか?
—— できません。乙B3号証(恐らく医学教科書の類)に、30度前後が適切と書いてあるが。
—— 直角三角形の定理・・・いや、この文献の記載はどう思うか?
—— ナンセンスだと思う。高角度で刺すことにより、対面壁に突き当たると言ったが、そういうことが被告にあったのか。
—— あった。普通なら、圧迫性血管痛は起こりえない。裁判長
最後に何か言っておきたいことがあればおっしゃって下さい。
—— 三平方の定理で典型的なところを述べます。斜辺イコール、垂直辺の2乗プラス水平線の2乗、の平方根の長さとなる。この辺をしっかりとご理解頂ければと思います。
何の理解だよw
この後、2~3分間、合議するのでお待ちくださいと言って、裁判官3人が裏に消えまして、何の合議かと思ったら、「合議の結果をお伝えします。原告から鑑定の申請がありましたが、採用しないこととしました。」とのこと。こんな事件で鑑定不採用に合議も何もないだろうと思ったけれども、そこら辺は手続き重視の裁判法廷ですね。
「弁論を終結します。判決は7月29日、木曜日、午後1時10分、場所は611号法廷です。○○さんはいらしてもいらっしゃらなくても構いません。いらっしゃらなかった場合には、書面をお送りします。」
最後まで御丁寧でした。