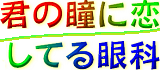令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
カテゴリー「医療訴訟」の記事
弁護士は懲戒請求ぐらいでガタガタ言うべきではない?
2018年12月23日
大元は,「ぽぽひと@常時発動型煽りスキル持ち」(平成30年12月23日時点での呼称。以下,ぽぽひと先生と記す)という弁護士の先生のツイートです。
医療過誤訴訟における医師の被害妄想でありがちなんだけど、実際は医療事故で医療側が敗訴するケースの何倍ものケースで医療側が勝訴してるし、その何十倍も訴訟提起すらせず断念してる事案がある。 https://t.co/J79n4O53dT
— ぽぽひと@常時発動型煽りスキル持ち (@popohito) December 20, 2018
「医療過誤訴訟における医師の被害妄想でありがちなんだけど、実際は医療事故で医療側が敗訴するケースの何倍ものケースで医療側が勝訴してるし、その何十倍も訴訟提起すらせず断念してる事案がある。」
とのことです。確かに,以下の最高裁発表の資料によれば,医療側が勝訴するケースは医療側が敗訴するケースの3~5倍程度となっています。
また,「その何十倍も訴訟提起すらせず断念している」という点は,統計があるのかどうか知りませんが,少なくともあながち間違っているともいえないだろうという肌感覚を私も持っています。
ぽぽひと先生は,「医師の被害妄想」だと述べられました。引用元ツイートには「世界一産婦が死なない国であるのに,死ねば産婦人科医は訴えられて負ける」と書かれており,訴訟リスクへの不安を述べたものと考えられるところ,それは被害妄想だということのようです。
このやり取りには若干の齟齬があるように思われ,全てをそのまま受け取るのは適切ではないと思いますが,少なくともぽぽひとさんが「医師の訴訟にまつわるリスクは高くない」ということを言っていると捉えて良いだろうと思います。
ところでここに,弁護士に対する懲戒請求事案の集計がありました。
これを見ると,懲戒請求された件数に対して,実際に懲戒された件数は概ね3%台と,極めて低いようです。細かく見るとさらに指摘できる点はありますが,ざっくりいって医師の訴訟リスクと比べて特段高いリスクということはないと言えそうです。
昨今話題になっている,北周二先生,佐々木亮先生らに対して内容不明の大量懲戒請求がなされた事件は論外と思い,私も一部カンパをさせて頂きましたが,そういう異様な事例は別として,基本的には懲戒請求は弁護士が意に介するほどのものではないと考えて良さそうです。しかも医師が訴えられれば医療の素人である法律家に裁かれ,多くの医師が到底承服できないような内容の判決を出されることがあるのに比べれば,懲戒請求は同業者による評価がなされるものであり,その点でも心理的な負担は軽いだろうと思います。
もっとも,私の考えでは,たとえ同業者による評価を受けるものであったとしても,負担は決して少ないというものではないと思っています。私が傍聴した以下の弁護過誤訴訟では,被告(弁護士)に敗訴する理由が到底あるようには見えないにもかかわらず,「これ以上被告乙1として,原告の請求に煩わされる時間が増えれば,事務所経営者として業務上取り返しの付かない損失を被る危険が」あると主張されており,少なくとも時間的負担は少なくないだろうとの印象を持ちます。
ぽぽひと先生は,医師が訴えられれば,異業種の素人に全てを説明しないとならず,大変な負担であるという現実に,少しは配慮した発言はできなかったのかなと思います。
また,医療訴訟について触れるのであれば,中には本当にとんでもない事例があるという現実も知ってもらいたいと思います。最悪の例は以下のものです。
「エホバの証人輸血拒否で死亡」報道の紹介記事問題
2018年11月15日
患者側で活躍する谷直樹弁護士が,7年前にご自身のブログで,「青森県立中央病院,エホバの証人信者の手術を打ち切り患者死亡」とのタイトルで,以下のようにコメントをしていました。
輸血は拒否しても,血液製剤は拒否していません.血液製剤を使用して手術を続行することはできなかったのでしょうか.
私は最初にこれを見たとき,エホバの証人は人間の体から離れた人間の一部は絶対に受け入れない,と理解していたので,血液から作られた血液製剤を拒否していないというのは筋が通っていない,と思い,ツイッターで,「・・・へ?」とコメントしました。
しかし上記は私の理解不足から来きたもので,エホバの証人の中には,赤い血の輸血はダメだけれども血液製剤は構わないなどと,中途半端な考えを持つ人もいるようなのです。
そうすると,この亡くなられた方も実は血液製剤は拒否していなかったという可能性はあるわけです。実際,拒否していたことを知らないまま「拒否していません」とは書けませんよね。
そうだとすると,谷直樹弁護士はどうしてこの亡くなられた方が血液製剤を拒否していないことを知っていたのでしょうか。報道にはそのようなことは書かれていません。
もっとも考えられることは,記事に登場する息子さんから,谷直樹弁護士が相談を受けていたということになるでしょう。そしてこの事件について,息子さんか谷直樹弁護士がマスコミに情報提供したということになるでしょう。病院がマスコミ取材に応じるにしても,個別の事例について,遺族の了解なしに取材に応じることはできないと思われます。
そうして報道されたものを,自身のブログで,「報道があったので掲載しました」という体(てい)で紹介するやり方はどうなんでしょう。
他にも谷直樹弁護士が受任して,提訴段階で報道があり,敗訴したからなのか判決については報道がないという事例もあり,そのようなマスコミの使い方をするところをみると,一方的だなと感じるところです。できるだけそういう例を掘り起こしていきたいと思っています。
相手取るべき相手を間違えているのではないか?
2018年10月30日
先週の傍聴です。東京地裁民事第14部,医療訴訟で事件番号は平成30年(ワ)第27653,期日は第一回弁論。
被告はB病院とC医師。
しかしB病院は,事件が起きたA病院から事業は引き継いだが別法人,職員も一旦退職して新組織としてやっている。A病院の債権債務は精算して国に返してしまって実態がない。そしてB病院はAと関係がない。
裁判長)被告とすべき相手を間違えているのではないか・・・でもC医師についてはその問題はないか。
被告代理人) 一応Cさんが入っているので,中身については入って頂いて,○○を継続しなければならないと思いまして。当事者適格は争わないが,誠実に争います。
原告代理人) 万一過失が認められて賠償金が認められた場合・・・ (峰村注:万一とか言うなよ,それほとんど勝てないって暗示じゃんかよ)
被告代理人) 渉外の交渉の時に権利義務の客体が違うというお話はお伝えしたつもりだったが・・・
感想: 原告代理人の訴訟進行スキルはどうなんでしょう,まあC医師も対象にしているからいいのかも知れませんが,僕ハラハラします!
少なくとも文献は出してもらったほうがいいと思います
2018年10月28日
東京地裁での医療訴訟第1回弁論メモ書きです。適当なメモで,しかも一部省きます。事件番号平成30年(ワ)第27514号。原告側は代理人一人の出席,被告側は欠席で答弁書擬制陳述。
裁判長: 原告の主張は・・・
原告代理人: 過失1は,乳癌手術をもうちょっと早くすべきだった,○年○月○日から数週間以内に。過失2は,抗がん剤の副作用云々。
裁判長:損害は自己決定権の侵害ですか? 今言われた過失との関係がわからない。
原告代理人: 手術が早かったらリンパ節転移は無かっただろうということ。それについての慰謝料との・・・
裁判長: 説明が不十分で,それによってどういう不都合があったというのでしょうか?
・・・
裁判長: 抗癌剤は特定されているんですか? どういうものでどういう副作用で,そういう医学文献は? 提出は?
原告代理人: 考えています。
裁判長: まだ準備していない? それはお出しいただいたほうがいいと思います。少なくとも文献は出してもらったほうがいいと思います。
感想: こりゃ,原告代理人は相当頑張ってもらわないとヤバそうですね・・・裁判長もまた心優しいご指導ですね。
熊本認知症患者転倒訴訟,判決内容概要
2018年10月25日
認知症患者が車椅子で一人でトイレに行き,トイレ内で転倒して寝たきりになった事故について,病院側の責任を認めて,2770万円ないし2780万円の賠償が認められたとして,広く報道された事件です。
入院中に転倒で賠償2780万円 熊本地裁判決、弓削病院の過失認定
医療関係者の間では,医療現場の責任を過大に認めたのではないかと大きく話題になりました。この事件について,知人が調べてくれたので報告します。
———————————————
熊本地方裁判所、訴訟番号:平成27年(ワ)第413号
原告被告ともに熊本市内だが、原告代理人は八代市。
原告は事件当時89才、転倒脳挫傷でA病院入院。回復期病院であるB病院へ転院。長谷川式0点 食事以外全介助 要介護5認定。易怒性および妄想など精神症状顕著であるため被告病院へ転院。手続き上は医療保護入院となっており相当な精神症状があった模様。
入院時病名は器質性精神病。入院時は転倒リスクレベル3(最大)の評価。
3月下旬に入院して4月に徐々に歩行能力向上した。
4月12日のケースカンファレンスで転倒リスクレベル2へ下げたので、安全ベルト(抑制)はやめた。
長谷川式はやっていない。
4月下旬には尿意を自己申告してた。かなりの頻尿が続いていた。
転倒事故は5月上旬連休中 午後8時ちょっと前。
病棟入院患者は40名 夜勤3名。
眠前薬の配布内服時間でデイルーム監視役は一人。
ほかの二人はほかの作業をしていた。
患者に薬を配布服薬させながら全体を監視。
被告がいなくなったことはわからなかった。
トイレで転倒して発見された。
頸椎損傷して両上下肢機能全廃。
今は別の療養病院に入院中。
誤嚥性肺炎もきたして気管切開とのこと。
娘(原告)は毎日付き添っているとのことで、付き添い費用も損害賠償請求項目に入れられていた。
【以下 判決文から裁判所の判断】
争点 1 過失の有無について
被告には原告を見守る注意義務があった。気が付かなかったから注意義務違反。原告がトイレの際に必ず声掛けしていたとの主張は、記録上単独行動もみられるので認められない。高度認知症なのだから声掛けを前提とした体制をおこなうべきではない。デイルーム監視役が監視に専従していれば十分だった。
院内のマニュアルに、「夜勤は4人で行い、うち一人は監視役に徹する」との旨の記述があり、また 事件後は4人体制としている。事件前は3人が常態だった。
(裁判記録では、40人のほかの患者の要介護度についてもちょっとした争点にはなっていた模様。)
監視役の准看護師の証言で,「患者に薬を配りながらでは注意は十分ではない」との旨の発言が判決理由に入っている。監視役専従を一人配置するべしとの結論。
争点 2 損害額
治療費 50数万 →争いなし。
付き添い費用 →医師の指示がなく 現在の入院先を原告(娘)自身が「完全看護」と言ってるので却下。
慰謝料・雑費→原告主張の7割 600万程度。(ブログ主注:慰謝料の詳細項目は不明)
逸失利益→最初から原告の主張になし。
後遺障害慰謝料→約2000万円
結局、後遺障害慰謝料約2000万円が金額としても論点としても最大だった。
元々重度認知症の人の完全四肢麻痺の後遺障害慰謝料(逸失利益ではない)。
被告の主張として、既存の障害に加重した場合は損害から差し引く(神戸地裁H20年9月5日)、逸失利益から既存障害を差し引く(さいたま地裁H25年12月10日)という判例の援用があったが、裁判所は,「元々重度認知症ではあったが、上肢機能に異常はなく4月から歩行能力も改善しており,認知症と四肢麻痺は同系列の障害ではなく、新規障害と判断するので損害は2000万円を下らない」との旨の判断をした。
訴訟費用は原告が3割、被告が7割負担。
争点 3 過失相殺
原告に事件当時、十分な事理弁識能力はあったとは認めがたい。しかし被告は認知症施設として重度認知症があることを前提として受け入れたのだから、これを前提として看護するべきである。
判決文では 一時的な安全ベルトの使用は認めていた。
【閲覧者感想】
重度認知症を過失相殺では責任ゼロにしておいて、損害認定では健常者と全く同様というところがポイントだと思う。
判決では 原告(娘)が入院時に転倒の危険性を全く聞いていなかったことも言及しており、入院時配布資料に明記しておくことも対策かもしれない。
論点にないところで興味深かったのは入院時と退院時の処方。
入院時:向精神薬4剤、α阻害剤(前立腺肥大)、抗コリン薬(頻尿)、降圧剤、下剤など
退院時:向精神薬はメマリー20㎎のみ。八味地黄丸も?、泌尿器科的処方なし。下剤と降圧剤など。
良心的な処方管理をしていると思われるが、法廷では一切論点になっていない。
——————–
【閲覧者感想2】
医療への無理解。
暴れる重度認知症患者が行けるところは多くない。受け入れるほうは大変だし採算も悪い。認知症という前提を重視しろということは、受け入れる患者を選べというのと同義。
おそらくそこに無自覚なのか、別問題といえば通るとでも思ってるんでしょう。法曹ならそこを逃れるロジックを展開しておくものでしょうが、それは探したけど見られず、そういう意味では稚拙。
損害計算の積算根拠や判断・前例は医事紛争にかぎらず 交通事故などの分野に共通のロジック・形式だと思う。ロジックとホンネの乖離があったりするフシがあったら、そこを突くとおもしろい。
医事だけを見てフォーマットを変更することは普通は出来ない
さらにいうと現実無視の判決ですでにサラ金業界をつぶしている。そういう反省も全くないところに清々しさを感じた次第。
民民の任意性の高い契約と医療を同列に扱っている。応召義務はこういう時には出てこない。
——————–
【処方について、別の医師の感想】
良心的な処方管理をしていると思います。向精神薬4剤だったのが無くなってる訳ですから。そのままの処方継続していたらガッツリ薬剤性の抑制になったり、薬剤性パーキンソニズムのために、トイレに自分で行くこともできなかったでしょうし、転ぶことも無かったと思います。
どう考えても、体の元気な認知症は「入院させると馬鹿を見る」って判決にしか思えません・・・。
——————–
【ブログ主感想】
注意義務についても医療側に厳しい判断だと感じるが、とりあえず措いておく。
別系列の障害だから後遺障害慰謝料もゼロから計算というロジックだと、一人の人が何度も高額の後遺障害慰謝料を得ることができることになる。そのロジックのもとでは、例えば異なる系列の障害で後遺障害等級1級を2回起こせば、一回限りの死亡事例よりも高額な慰謝料を得られることになり到底公正とは言えないと思う。後遺障害等級を認定する際に異なる障害を併合して上位の等級を認定するルールがあることとも整合しない。
認知症が事故を起こした大きな要因となったと判断できる例であるにもかかわらず、過失相殺を認めていない点は、日本の司法慣行としてしばしば見られることだと思うが、司法水準にかなった判断とは直ちにはいえないと思う。そもそも過失相殺は,当事者からの主張がなくても,裁判所が判断できることになっている。韓国の裁判所なら、黙っていても5割・8割の責任制限(素因減額・過失相殺の類推適用)があると思われる事例であるが,日本ではどういうわけかもともと弱っている方の事故であっても,健康な方の事故と同じように計算されることが多い印象。