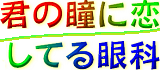令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
カテゴリー「医療訴訟」の記事
弁論終結の予定日に新証拠を出そうとする弁護士
2011年9月21日
平成23年9月14日の傍聴記です。まずは東京地裁民事第35部、事件番号平成23年(ワ)第25250号、第1回弁論。原告代理人のみ出廷。2年前にも代理人同士で直接相談したことがあり、時間が経ってしまった事案で、被告病院からはカルテがないので対応できない旨伝えられているという。医学的に簡単な事案ではないとも言われていた模様。当時の医師もいないと。今回、カルテがない旨の内容証明郵便も届いているとのこと。原告側、これで訴訟提起をして、やっぱりカルテが本当になければ、慶應病院などのカルテ等で一方的に理解して主張するかもというような話。訴状に対する被告側の出方次第だとも言う。無理じゃねーの?お次は東京高裁第23民事部、事件番号平成23年(ネ)第1909号、弁論。本日弁論を終結しようとしていたところに、控訴人(一審原告)が新証拠を提出した模様。それも医学的意見書か何かの結構な証拠らしい。被控訴人側からは、証拠採用をするならばこちらも準備して反論しなければならないので終結は困る、とのこと。裁判官3人合議のため一旦退出の後戻ってきて、「終結して、被控訴人の今の主張についても判決で判断をします」との旨を述べられた。つーことは控訴棄却でしょうw つーか終結の日に出すなよ。患者側弁護士とかが医療事故調とか騒いでいて、それはそれでいいんですど、弁護事故調も同時進行したほうがいいんじゃないですかねぇ?
まただよ@谷直樹弁護士@苫小牧市立病院の事例
2011年8月31日
例の、法的過失の理解が怪しい谷直樹弁護士のブログからですが、苫小牧市立病院,気管切開でカニューレが適切に挿入されず死亡した件で示談とのことです。
まずはお亡くなりになった女性のご冥福をお祈りします。
さてブログ記事によると、
市は「重大な過誤、過失はなかったが、気管切開手術が死亡要因であることは確か」としている。
とのことなのですが、病院側がそのように考えているとなると、少なくとも市側から進んで補償をすべき根拠はないと思われます。
ところが谷直樹弁護士によると、
厳密にどの行為に過失があったのかを具体的に特定することはできなくても,気管切開を行って,カニューレが適切に入らなかった(入れられなかった)という事情から,補償をすべきというのは,常識的な考え
だというのです。
示談金は500万円だそうですが、そのお金はもともとは市民の税金や病院の収入でしょう。脳出血で意識障害を起こし血腫の除去手術を受けたが、症状は改善されなかったという方の処置で、かつ重大な過誤、過失はなかったという事例に対して、金銭を支払って示談するのは如何なものでしょうか。苫小牧市民は、これによって市政や市民病院の診療原資が500万円分下がることに対して、疑問を抱かないのでしょうか。
このような例を見ると、いつも不思議に思います。
何が正しいのかわからない賠償判断
2011年8月24日
最近その存在を知って注視している、谷直樹さんという弁護士のブログがあります。
そこに、山形大学のカテーテル事故についての報告とそれに対する谷直樹弁護士の見解が掲載されました。
右室壁の穿通を引き起こしたことについて,臨床実務的に明らかな手技上の問題があったとは言えないが,「過誤」があった(すなわち,賠償する)との判定です. この判定の仕方は正しいと思います.
いや・・・
この判定のどこが正しいのか、何をもって正しいと考えているのかがよくわかりません。少なくとも、法的判断としては成り立たないものでしょう。つい最近、私のサイトで「手術の合併症と法的過失」について記事をアップしたところでした。
もしかすると、社会的にはそうあるべきという理想論を述べているのでしょうか。そうだとしたら紛らわしいですね。弁護士を名乗って書かれいているブログなのですから、「法的に正しい判断だ」と誤認されるおそれがありそうです。この記事を見て「この先生なら頼れる」と信じて依頼をして、裁判では案の定負けた、という人が増えないことを祈るばかりです。法律家としての説明責任が問われる記事だと思います。
習熟していないのはどちら?
2011年8月3日
今日の東京高裁で医療訴訟の第一回口頭弁論を傍聴、事件番号は平成23年(ネ)第2903号。
控訴人が患者関係者、被控訴人が病院側なので、おそらくは地裁で患者側が敗訴したのでしょう。
通常、控訴審というものは、地裁で一度決着している事件の再確認なわけですから、よっぽど逆転につながるような証拠がなければ、地裁と同じ判決が出ることが多く、そのため実際には、第一回口頭弁論でそのまま結審して次回は判決という場合が少なくありません。
さてこの事件、どうやら高裁に移ったあとに原告側から匿名の意見書が出されたようです。井戸端会議であれば匿名の意見だって別に構わないわけですが、裁判というものは、ある人からある人に金銭を国家権力をもって半強制的に移動させるか否かを争うものですから、その国家権力発動の根拠が匿名というのでは権力の横暴にもつながりかねませんから、その取扱いは難しい物があります。それでもこの事件では、わざわざ病院側がその匿名意見書に対して反論書(第1準備書面)を提出したそうです。どうやら匿名意見書が1週間前に出され、病院側の反論書は昨日に出されたようです。
そこで、今日は患者側がその反論書に対して再反論をしたいというのです。それも、今日のこの法廷で口頭で。患者側が「反論書を昨日受け取ったばかりなので」との旨を弁明すると、裁判長は「あなた方が(意見書を)出すのが遅くなったのでこうなったんでしょう」との指摘をするのでした。患者側は、それでもとにかく口頭で主張を述べるので、それを調書にとってもらいたいということで、一応裁判長も了承しました。
で、ひとしきり再反論を述べると、今度は病院側が再々反論をしたいというのです。恐らく裁判長は既に勝負ありと踏んでいたと思われ、「もういいんじゃないですか」との旨が告げられましたが、病院側が「一言ずつだけ」というので、それも裁判長から了承されました。実際には病院側が再々反論を始めると、そんなに短くはなかったため、「一言じゃないじゃないですか」とのツッコミが入れられていました。
ポイントは5点ありました。大雑把で不完全ですが書いていきます。「再反論」が、患者側の主張です。
反論書「肺に酸素が入らなくなっていた状態が継続していたということに根拠はない」
再反論「気管内挿管後のSp02の数値の回復度が、酸素が入らなくなっていた根拠になる」
再々反論「原疾患が関与しており、そのことだけを以て、肺に酸素が入らなかった根拠とするのは失当」
反論書「なぜ13:40-13:41の間は脳が低酸素状態ではなく、13:47には脳が低酸素状態だったと言えるのか」
再反論「この間の6-7分の間に限界を超えたからだ」
再々反論「何ら科学的根拠がない」
反論書「呼吸停止について(・・・聞き取り不十分)」
再反論「何もしていなければその通りであるが、その間に人工呼吸されていることにより、不可逆的な障害が始まるものではない」
再々反論「原疾患が関与しており、担当医の義務違反のみに帰するのは失当」
反論書「(・・・聞き取り不十分)」
再反論「気管内挿管を6-7分怠ったため」
再々反論「無策のまま6-7分経過したわけではないことは、これまでに主張してきた通り」
反論書「(・・・聞き取り不十分)」
再反論「空気の入らないような人工呼吸をするのは、習熟していないということ」
再々反論「(・・・聞き取り不十分)」
詳細はわからないですが、患者に何らかの急変が起きたということのようです。最後の方は傍聴するのがバカバカしくなってきたのですが、担当した医療関係者について「習熟していない」などと主張するのを聞くと、そういうあなたの医療訴訟担当習熟度はどれくらいなのかな?なんてツッコミたくなりますね。まあそういった例は、枚挙にいとまがないんですが。
蛇足ですがこの事件の右陪席裁判官が、以前に地裁で傍聴した、風俗店を舞台にした大変面白い貸金返還訴訟の裁判官だったので、ちょっと嬉しくなりました。
インプラント手術で女性死亡
2011年8月1日
まずはお亡くなりになった女性のご冥福をお祈り申し上げます。
この事件に対して、谷直樹法律事務所のブログに記事が書かれています。
この記事を見ると、「泣き寝入りで終わらせることのないようにしないといけませんね.」として、その後に説明義務違反が認められた事例や、手技上の過失が認められた事例が例示されています。
裁判で負けた事例についての言及はありません。
負けた事例をあわせて紹介することが義務というわけではないでしょうが、こういう記事の書き方を見ると、「ホラ、こんなに責任が認められた例があるんですよ」という、弁護士側から見ればうまく行ったという例だけを例示して、責任が認められなかった例、つまり弁護士側から見ればうまく行かなかった例を例示していないという、バランスの悪さに嫌悪感を催すというものです。
まあ、美容外科のホームページも似たり寄ったりですから、一方ばかりを責めることはできないとは思いますが、司法の「自分に甘く、他人に厳しい」態度には、いつもながら違和感を感じます。私としてはこの辺の注意喚起を、医療訴訟の原告の方へのアドバイスや、裁判官の方々へのメッセージとして私のサイトにアップしています。
谷直樹法律事務所のブログには、私からすると香ばしい記事が満載されており、今後も注目して行きたいと思います。