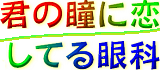令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
受精卵の逸失利益とは…?
2010年10月6日
不妊治療中の夫婦の,培養器で培養されていた5個の受精卵が,予定されていた停電の対策を病院側が怠ったために使えなくなったため,夫婦が病院側を訴えた,という事件が報道されました。
培養器事故で受精卵5個成育不能 弘前大を提訴 青森の夫婦
培養器事故で受精卵5個成育不能 弘前大を提訴 青森の夫婦
担当医の過失による培養器の事故で受精卵5個が育たなかったとして、青森県弘前大病院(弘前市)で不妊治療を受けた青森市の夫婦が30日までに、弘前大に対し、受精卵から生まれる可能性があった子ども5人分の逸失利益や慰謝料など計1830万円の損害賠償を求める訴えを青森地裁弘前支部に起こした。
訴状によると、同病院の担当医は2008年10月、原告夫婦の体外受精を実施。受精卵5個を培養器に入れたが、数日後に培養器の電源が切れる事故があり、受精卵の成育が不可能になったという。
原告側は「担当医の過失で事故が起きた」と主張。受精卵の着床や出産のリスクを考慮した上で、受精卵から生まれる可能性があった子ども5人分の逸失利益を計400万円と算定した。損害賠償のほか、学長名での謝罪文と東北地区の産婦人科学会への事故報告を求めた。
原告側は訴状で「5人の子どもを医療事故で亡くしたと感じ、大きな精神的ダメージを受けた。病院側の不誠実な対応でさらに傷つけられた」としている。
病院側は「培養器の電源が切れたのは事実だが、弁護士と相談中で詳しくコメントできない」としている。2010年08月31日火曜日 河北新報社
毎日新聞には,「同日は電源点検のため停電実施日だったという。」と書かれており,予定された停電であったことがわかります。そうすると,その停電に対する対策を怠ったために受精卵が使えなくなったことについては,病院側に落ち度があったと言えそうですから,このご夫婦の悲しみと怒りは理解ができます。
しかし,理解できないのは訴額,とりわけ受精卵の逸失利益です。受精卵5個で400万円ということは,1個あたり80万円になります。普通の訴訟であれば,受精卵よりもさらに成長した胎児であっても,逸失利益は認められないものと認識していたのですが,このご夫婦はそうではないと主張されているようです。もしも受精卵が実際に新生児として出生し,成人して賃金を得ることを考えているならば,逸失利益は一千万円ないし数千万円という計算になるはずです。本当に摩訶不思議な主張と言わざるを得ないと思っていました。
そうしたところ,これに対して病院側が反論したことが報道されました。
弘前大学医学部付属病院で受精卵が成育不可能になったのは培養器管理に過失があったとして、
青森市内の夫婦が同大に1830万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、
青森地裁弘前支部(村上典子裁判官)であった。大学側は請求棄却を求める答弁書を出し、争う姿勢を示した。訴状によると、夫婦は不妊治療を受けていたが、08年10月12日、受精卵5個を入れた培養器の電源が落ちて温度が低下し、全受精卵が成育不可能になっているのが見つかった。精神的損害は甚大だと主張している。
大学側は答弁書で、因果関係の主張立証内容が不明瞭(ふめいりょう)などと指摘し、受精卵について逸失利益を算定できる法的根拠の明示などを求めた。【塚本弘毅】
毎日新聞 2010年9月23日(木)
(赤文字はブログ主による強調)
これを見ると,ご夫婦は根拠を示さずに逸失利益の主張をされたのだということがわかります。こういう行為を医療に例えるなら,根拠のない治療方法を闇雲に開始するようなものと思われます。医療でそのような行為を行えば倫理的に批判を免れないことは勿論,それによって損害を発生させれば,賠償責任を負わされて当然と言えるでしょう。受精卵の逸失利益の主張を,ご夫婦が自ら考案したのであれば別ですが,代理人弁護士が繰り出したのであれば,その姿勢は如何なものかと思うのですが如何でしょうか。
ちなみに,請求金額1830万円の場合,標準的な着手金は100万5000円になるようです。あくまで想像ですが,着手金を約100万円に揃えるために,慰謝料1300万円+弁護士費用130万円では足りない分を,むりやり逸失利益として捻出したように見えてしまいます。ただ,そのように考えた場合,(1)なぜ弁護士費用を慰謝料と逸失利益の和に対して1割と計算しなかったのか,(2)なぜ着手金がきっちり100万円になるようにしなかったのか(慰謝料1200万円+弁護士費用120万円+逸失利益500万円),というツッコミが入りそうです。
普通に考えれば,悪ければ敗訴,良くても慰謝料100万円がせいぜいの事案に思われるのですが,着手金が100万円になるような訴額での提訴というのは,如何なものでしょうかね?
前回記事の判決について追記
2010年10月4日
ゾウの時間・ネズミの時間として記事にした件ですが,新小児科医のつぶやきというブログでも取り上げられ,様々な意見が出ました。そこに私も少し書いたので,こちらでまとめておきます。
記事を改めて読んだところ,判決の「過失がなくても後遺症が残った可能性がある」という部分に注目が行ってしまい,ちょっと誤認のある感想を書いてしまいました。以下のとおりです。
これは,最悪ですね。
皆さんご存知の通り,法的責任を認めるための過失因果関係の認定には,「過失があったから損害を被ったことの高度の蓋然性」の証明が必要です。そしてその証明は,僅かな疑義を挟まない程度の科学的な証明ではなくても,通常人でも疑いを挟まない程度の証明である必要があります。
ところが引用された部分には,「「過失がなくても後遺症が残った可能性がある」として損害額の3割を減じた。」と書いてあります。
過失がなくても後遺症が残った可能性があるというのですから,通常人でも容易に,過失と障害との因果関係に疑義を挟む(むしろ挟まないのが異常)と言うべきものです。
この裁判官には,通常人程度の論理的思考能力が欠けていたものと断言して差し支え無いと思われます。
この裁判官は,裁判官に向いていないと思います。
その後に読みなおしたところ,「過失がなくても後遺症が残った可能性がある」とはするものの,過失と死亡との因果関係は,後遺症の有無とは別に認めたのだろうと気づきました。そのため,以下のように訂正を書きました。
あー,激しく恥ずかしい読み違いをしていました。
判決では,過失があっても後遺症が残った可能性があると判断しているけれども,過失がなければ死亡はしなかったという判断なのですね。
しかしそうなると,「損害額の3割を減じた。」という判断の仕方は,一体どういう理屈によるんでしょうかね? 通常なら,「賠償金額」=「過失があった時の損害額」ー「過失が無かった時の損害額」という判断をすると思われますが,ここでざっくり3割引という判断をする根拠がわかりません。是非とも判決を読みたいものです。事件番号が分かる方がいらしたら,教えてください。
さらに,どうにもこの損害額認定の手法が胡散臭く思われたので,追記しました。
「過失がなくても死亡した可能性がある」と判断すると,因果関係認定ができないから,死亡したのはあくまで過失があったからだと判断して因果関係を認定しておいて,しかし実際のところは,証拠類からは過失がなくても問題が起きた可能性を否定するのも難しいので,それを後遺症の可能性とだけ認定して,賠償額減額の理由に持ってきたということでしょうかね。巧妙な手口に思いますが,これ以上は判決文や裁判記録を読まないと何とも言えませんね。裁判官がペテン師である可能性は否定できないと思います。
ま,ペテン師は言い過ぎで,法令ギリギリにうまいこと言いくるめたという程度かも知れませんが,報道から読み取る限り,通常の損害額認定のやり方からはかなり外れていることはまず間違いないと思われます。ベースには,通常の民事訴訟における過失因果関係認定のあり方が,医療訴訟にはうまく噛み合わないという問題があると思います。
尤も,それ以前に,医師の過誤を安易に認定する一部司法の過誤が問題なのだと思います。司法の過誤の例は,医療裁判・医療訴訟に既にいくつか挙げてあります。
ゾウの時間 ネズミの時間
2010年9月14日
初診の問診が不十分であったことが過失だそうですが・・・
初診開業医に賠償命令
地裁 患者死亡「問診が不十分」髄膜炎の症状を見過ごされ、治療の遅れから転院先で死亡したとして、境港市の男性会社員(当時40歳)の両親が同市内のたけのうち診療所(閉鎖)の50歳代の男性医師に慰謝料など約7500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、地裁米子支部であった。村田龍平裁判長は「十分な問診と、設備の整った医療機関への移送を怠った過失があった」として、医師に約5600万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2001年12月、高熱や嘔吐(おうと)の症状を訴えて初めて同診療所で受診。解熱剤などを処方されて帰宅したが、症状は悪化し、翌日に救急搬送された病院で細菌性髄膜炎と診断された。その後、意識が回復しないまま、転院先の病院で05年1月に多臓器不全で死亡した。
診療所では、感染症検査などを外部に委託しており、村田裁判長は「髄膜炎と断定することは困難だった」としたうえで、「髄膜炎を疑って特有の症状を確認するなどし、病院での検査を勧めていれば死亡は避けられた」と判断。一方で「過失がなくても後遺症が残った可能性がある」として損害額の3割を減じた。
原告側の高橋敬幸弁護士は閉廷後「初診患者に対する問診の不十分さと死亡との因果関係が認められるのは極めて珍しい。初診の重要性を開業医に投げかける判決だ」と話した。
被告側の川中修一弁護士は「短時間の診療で髄膜炎と見抜くのは難しい。医師と相談し、控訴を検討する」としている。
(2010年9月14日 読売新聞)
この担当医の問診が過失なら,この事件の一審・控訴審判決やこの事件の控訴審判決や,この事件の地裁判決なんか,過失もいいところじゃないかと思いますけどね。年単位で時間をかけられる裁判の中では,裁判官が勉強する時間はいくらでもあったわけですからね。
こういう例なら,裁判官に対する国賠で勝つ可能性がもしかしてあるんでしょうか? こういう例なら国賠で勝つ可能性があるというなら,司法は回らないと思うんですが。
専門家の判断を,あと出しジャンケンで法的過失認定するような国では,マトモな医療は存続し得ないと思います。
判例タイムズ1326「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム」
2010年8月26日
判例タイムズ1326号に,「医療界と法曹界の相互理解のためのシンポジウム 第1回」という特集が掲載されました。平成20年10月24日に開かれたシンポジウムで,東京地裁医療集中部4箇部の部総括判事が全員ご出席(孝橋宏判事,秋吉仁美判事,村田渉判事,浜秀樹判事),それに加えて帝京大の森田茂穂医師,昭和大の有賀徹医師,医療問題弁護団の安原幸彦弁護士,医療側の棚瀬慎治弁護士など,すごいメンバーのシンポジウムだったようです。話題は以下の小見出しから分かるようにかなり広い範囲を網羅しており,内容も大変面白くておすすめです。
ただ,読んだ感想としては,「このシンポジウムに集まられた判事の方々がされるようなハイレベルな仕事が,全国すべての裁判所でなされていたのなら,事態は現状ほどまでには深刻になっていなかったのではないかな」というのが真っ先に思うところです。あと,今回は過失判断についてはさておいて,因果関係に的をしぼってのシンポジウムだったとのことで,過失判断に関する議論も改めてなさって頂きたいものだと思った次第です。
文中小見出し抜粋
●民事裁判と刑事裁判の異同
●証明すべき事実――損害賠償請求の要件
●証明責任・立証責任ということ
●民事裁判で証明できたとはどんな場合か?
●要件事実とは何か?――証明の対象
●民事訴訟における事実認定の一般原則
●東大ルンバール事件の判決内容の位置付けとよくある誤解
●民事通常事件における事実認定の実際
●因果関係に関する判例理論
●議論の対象は事実的因果関係の有無
●最高裁判例のポイント (峰村注:最高裁判例平成11年2月25日)
●医療訴訟の特殊性――医学的知見の取扱い
●証拠の優越説と高度の蓋然性説の違い
●高度の蓋然性の内実について
●民事裁判における割合的心証の取扱い,請求額と認容額の違いについて
●東大ルンバール事件判決に対する違和感の原因について
●手技上の過失による結果と説明義務違反との関係について
●医療訴訟における原因と結果の解明について
●因果関係についての考え方の民事と刑事での異同について
●東大ルンバール事件判決の背景について
●優れた医学文献による裁判の必要性について
●インフォームド・コンセントの問題に関する原告側の視点等について
●インフォームド・コンセントの内実の確認について
●適切な争点整理の必要性などについて
●医療と司法のコミュニケーションの必要性について
●民事裁判に対する医療側の協力(お願い)について
過失がないのなら和解金は出すべきでない
2010年7月15日
大牟田市民病院:06年小児病棟死亡、330万円で和解 /福岡
大牟田市民病院は9日、06年に小児病棟で死亡した女児の家族から過失責任を問われ、5868万円の損害賠償を求められた訴訟で、見舞金330万円を支払い和解することを決めた。
病院によると、生後6カ月の女児が敗血病の疑いで06年4月8日に入院し、2日後に容体が急変して心筋症とみられる死因で亡くなった。女児の家族は「担当医師は病状の悪化を予測して適切な対応をすべきだった」として08年3月、福岡地裁に提訴。病院側は「適切な検査や治療を行い過失はない」と主張。今春、地裁が和解案を示していた。
医療安全対策室は「過失はないにしても、患者が亡くなったのは事実。冥福を祈り、和解したい」と話した。
〔筑後版〕毎日新聞 2010年7月10日 地方版
病院側は最後まで、過失は無かったと主張されているようなので、それを前提に書きますが、
過失が無かったのであれば、和解金を出すべきではないと考えます。過失がないのになぜ金を出さねばならないのでしょうか。
むしろ、過失が無いような事故について民事責任を問うことを請け負った原告代理人弁護士のほうに、事案の調査が不十分であった過失の可能性が考えられると思います。弁護士の訴訟前調査の不備を検討し、それ相応の過失があるのであれば、その弁護士が和解金相当の見舞金でも負担したらいいのではないでしょうか。医師にも過失がなく、訴訟を請け負った弁護士にも過失がないのであれば、患者遺族が耐えるしかないのではないでしょうか。
>医療安全対策室は「過失はないにしても、患者が亡くなったのは事実。冥福を祈り、和解したい」と話した。
病気で人が亡くなっていくのは当たり前のことです。それを遺族が騒いだからと、謂れもない和解金を払うようでは、運命を耐えて医師に恨みを向けないような大多数の遺族との間に、不公平が生まれます。
この医療安全対策室の担当者の発言は、問題だと思います。