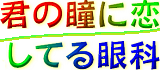令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
カテゴリー「医療訴訟」の記事
嘘を言わないと言ったじゃないですか!
2012年2月15日
東京地裁で今日傍聴した事件です。原告席には濃いサングラスの女性が一人・・・
ニキビエステ訴訟の原告敗訴
2011年12月21日
本年10月19日に傍聴した事件で、ツイッターで概要を簡単に報告した事件です。本日原告敗訴判決が出たので、まとめて報告しておきます。傍聴当日に書いたツイッターでの報告は以下のとおりでした。
今日東京地裁で見た裁判。18歳女性、ニキビ顔にケア液でエステして却って悪化。ケア液の会社とエステティシャンが共同で12ヶ月分の治療費を出した。状態は一進一退し、治療を担当した皮膚科医も、「会社側はもう十分誠意を尽くした。今の症状はケア液と因果関係はないと思う」と進言し、会社側らが治療費負担をを終了したところ、その後の治療費を支払えとして、女性が会社側を訴えた。傍聴席に母親と思しき人物らがいて、被告の証言にいちいち「嘘言っちゃって笑っちゃうわね」的な反応を見せる。人証調べを終了し、裁判長が弁論終結を宣言すると、原告代理人が「主張をまとめるので、あと一回弁論期日を希望」した。裁判長がそれを採用しないことを宣言すると「ちょっと腑に落ちないところがあるが」云々を言い出す始末。あんたがこの事件を請け負ってることのほうがよっぽど腑に落ちんわ。事件番号は平成22年(ワ)第45106号。
原告代理人だらだら尋問、予定60分のところを90分
2011年12月13日
平成23年11月2日に、担当医の証言を傍聴した事件です。
整形外科の術後12日目に肺塞栓を発症し、出血リスクが高かったためヘパリン2万単位のDIVを施行したところ、翌日に脳出血を来したということのようです。眼科医の私にはあまりよくわかりませんが、仕方がなかったんじゃないのかな?という印象でした。
原告代理人は、予定時間60分を大幅に上回る90分の尋問で、同じことを何回も何回も聞いていました。とにかく、心エコーをしなかった所で過失を認めさせたいということのようでした。
原告側の質問はほとんど、カミヤ弁護士という女性弁護士がしていましたが、その隣に座っていたのが、伊藤紘一弁護士でした。
http://www.itoh-law.com/100/
—————————-
7月10日10時30分、第1アタック
vital安定、意識清明
胸痛→AAA、AMI、肺塞栓鑑別
AMIは否定的だった。
CT施行。肺塞栓診断。
ヘパリン投与 アドバイス。
整形外科、放射線科チームと相談。
2万単位DIV
出血リスクが高かった。
整形外科手術後12日目。
骨を開けて手術した。
ヘパリン
APTT値延長 1.47まで
7月11日 4時 第2アタック
意識(-), ショック状態
脈、呼吸(+)
CPA(-)
心停止に近い状態。
脳CTと循環 どちらを優先→循環
先生の対応は ABCをした。
Bは酸素投与と人工呼吸
その後に検索。肺動脈造影
肺塞栓症
カテーテルを肺動脈に挿入。血栓溶解
血栓溶解不十分→ICUで持続的にした。
その前にフィルター留置
23:00~0:00頃、(医師が)病院を退去
「隣のホテルに待機しているので、携帯に連絡を」
連絡はなかった。
23:00に最終診察。
神経学的所見 異常(-)
7:00頃 看護師から瞳孔所見異常
対光反射遅延
自発呼吸(+)
脳死ではない。
鎮静薬を注視した。
意識は戻らず。
血栓溶解療法していたので、出血を疑い、頭部CT
出血性脳梗塞
大脳半球に広範な脳梗塞
家族同意→転院
原因は肺塞栓 右→左シャントで
卵円孔開存の可能性 血栓が飛んだ。
当時は確認されていなかった。
その可能性が高いと。
第二次アタック 主人から なぜ眠った状態か?→ 鎮静薬で眠っていると説明。
2週間で出れると説明。
亡くなるかも、緊急手術かも、人工心肺かも、と説明。
原告から、第1時アタック時に血栓溶解療法を施行すべきだったと言われているが
→ 全くそう考えない
右心機能不全、出血リスク → 抗凝固療法単体がすすめられる状態。
右心機能不全は、レントゲン、ECG、CTで確認した。
心エコーはしていなかった。
心エコー単独では判断しない。
心エコーで右心機能低下なら血栓溶解療法をしていたか?→そんなことはない。
意見が分かれる。
原告側 クニエダ医師意見書
第1次アタック後 肺動脈(圧?)上昇(-)
→エコーではわからなかった。
放射線科医師から、「血栓が沢山→抗凝固療法をすべき」とは?
→ 言われていない。「するべきではない」と
第2次アタックは予防できたか?
→言い切れない
第1次アタック発生時、第2次アタックの可能性は?
→高くはなかった
原告は低酸素脳症で
CPAではなかった。頸動脈はずっと触れていた。手足は動いていた。
右心負荷がなかったこと
心エコーしていない
→ 臨床症状、臨床所見で。総合的な判断。
CTには白い部分はなかった
→ あったと記憶している。
ここまで説明しても説明義務違反?!
2011年12月10日
ETSの説明義務違反で、110万円賠償の判決が出た事例の続報です。
事件番号は、平成21年(ワ)第55号、裁判長は高橋譲判事でした。
判決文をざっと確認してきたので、その説明内容と、それに対する判断などを記します。
————————
患者に交付したビデオ内容(患者はそれを見たことも確認されている)
手術後長期にわたって残る続発症は、ETSがもたらす効果の裏返しの関係にあり、手の汗を止めて快適な生活をするには、ある程度の負担の覚悟が必要。
最も頻度が高いのは、背中や腹部、さらには臀部などの発汗が増加する代償性発汗。個人差があるが、ETSを受けたほとんどの人に起こる。
パンフレットの記載内容
ETSの効果が半永久的に続くのと同様に、副作用も長期間続く。手術の効果が及ばない範囲である腰や臀部、下肢の汗の量が手術前より増える。ETSを行うと顔や手などの胸より上の部分の汗が止まるため、それより下の部分の汗の量が増える。ほとんどの患者に起こるが、代償性発汗を自覚しているのは約3分の2の患者。つまり、手術後には足の汗が増える可能性が高いということである。
直接の説明
ETSの内容、手掌からの発汗が止まること、ETSの副作用を説明。代償性発汗については、胸より上の汗が止まること、胸より下の汗が増えること、程度は人によって異なること、ETSを実施したほとんどの場合に代償性発汗が発症することを説明した。
代償性発汗の量がどの程度になるか、重篤な代償性発汗を発症することがあることについては説明をしなかった。
原告はホルネル症候群について最も気になっていて質問したところ、めったにないと回答した。代償性発汗で止まった部分の汗が体の他の部分から出るとは聞いていたが、出なくなる部分の汗がどのくらいの量であるかについては特に質問しなかった。
——————–
説明内容等に対する裁判所の判断
平成10年当時の発汗量の評価は、患者本人の訴えによる主観的な評価に依存している。手術後や治療効果を判定するためには客観的な評価が不可欠と考えられるが、その報告は少ない。
原告は、ETSで手掌多汗症が治ったこと自体には満足している。
適切な説明を受けていれば本件手術を受けていなかった、とは認められない。
平成10年当時にも、ETS術後に日常生活に支障があると訴えた患者はいた。当時NTT関東では手掌多汗症の患者が大量で手術は2年待ち。多数の手術経験があったと推認できる。ETSで重篤な代償性発汗が、ETSを行う医療機関の間で一般的な認識になっていたとまでは言えなかったとしても、NTT関東の医師においては、文献調査が十分可能であった。現に、平成7年までには、精神的に問題がある患者であったとはいえ、社会生活不能な事態に陥った症例や、ノイローゼになった症例を経験していた。
——————–
平成10年当時の発汗量の評価は、患者本人の主観的な評価に依存していたようです。そうすると、普通に考えれば代償性発汗についての覚悟を促す内容となっているこの術前説明は、その治療を受けるか否かの利害得失を検討するのに必要かつ十分な情報を提供したものと言って差し支えないでしょう。
さらに言えば、平成10年当時には、「ETSで重篤な代償性発汗が、ETSを行う医療機関の間で一般的な認識になっていたとまでは言えない」そうです。この点からも、「日常て生活に支障をきたすほどの代償性発汗を発症することがありうること」を説明しなかったことについて、過失を認めるには足りないと思われますし(裁判所もこの点での過失を認めているわけではないようですが)、多数の手術をこなしていたNTT関東病院での術後に社会生活不能な事態に陥った症例は、精神的に問題があった患者だというのですから、やはり「重篤な代償性発汗発症の危険性が一般に起こりうること」まで説明をしなかったからといって、過失を認めるということにもならなさそうに思います。
どうやら裁判所は、NTT関東(というかこの術者)はETSを多数行う専門性を持っていたのだから、文献調査を徹底的に行なってその危険性を伝えておかなければならなかった、ということを言っているようです。しかしこれも不思議なことで、ETSを多数行う専門性を持っているのであれば、どちらかと言えば情報提供側になることが多いと考えられますが、裁判所は逆のことを考えているのでしょうかね。医学的知見の拡散についての認識に、ちょっと無理があるように思いますがね。
なんにしても、この事例で無責判決(原告敗訴判決)ならば無理なくスッと書けると思われるのに、この判決は無理を重ねて有責判決に仕立て上げられた、いわば原告にいくばくかの花を持たせるように無理を重ねたと感じられて、いかがわしくて仕方がありません。
先日は判決文だけしか見れなかったので、後日、他の記録も見てみてから更に検討したいと思います。
手術を思い止まらせるのが説明義務なのか?
2011年11月25日
今年(平成23年)の6月に傍聴した事件と思われる、多汗症に対する手術の説明義務が争われた事件の判決が出たようです。事件番号は平成21年(ワ)第55号でした。
共同通信の配信によると、
判決は「ETSの後では、別の部位から多量の発汗があり日常生活に支障が出るなど、術前より苦痛を感じる場合があることを医師が説明していなかった」と過失を認めた。
と、説明不足があったという判断だそうです。
しかし、私が原告本人と、担当医師の尋問を両方聴いたところでは、手術そのものは成功して手掌の発汗は止まったそうですし、術前には代償性発汗の説明があって、原告本人も、乳首のラインより上から出なくなった分が乳首より下の部分から出るようになることを、術前に説明を受けて認識していたということでした。さらに言えば原告は術前に説明ビデオなどを渡されて、検討する時間も十分あったそうです。
それだけ説明してなお、「術前より苦痛を感じる場合がある」という説明が義務だという理由が、皆目見当がつきません。「乳首のラインより上から出なくなった分が乳首より下の部分から出る」という具体的な説明をしてありながら、なお「術前より苦痛を感じる場合がある」という抽象的な説明する義務を科すような判断というのは、我々の理解を超えています。
東京地裁民事第14部、高橋譲裁判長。以前からちょっとアレ気なところを感じていましたが、いくら何でもひどいんじゃないでしょうかね? 後日判決文を読んで、改めて報告することになると思います。