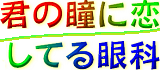令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
ここまで説明しても説明義務違反?!
2011年12月10日
ETSの説明義務違反で、110万円賠償の判決が出た事例の続報です。
事件番号は、平成21年(ワ)第55号、裁判長は高橋譲判事でした。
判決文をざっと確認してきたので、その説明内容と、それに対する判断などを記します。
————————
患者に交付したビデオ内容(患者はそれを見たことも確認されている)
手術後長期にわたって残る続発症は、ETSがもたらす効果の裏返しの関係にあり、手の汗を止めて快適な生活をするには、ある程度の負担の覚悟が必要。
最も頻度が高いのは、背中や腹部、さらには臀部などの発汗が増加する代償性発汗。個人差があるが、ETSを受けたほとんどの人に起こる。
パンフレットの記載内容
ETSの効果が半永久的に続くのと同様に、副作用も長期間続く。手術の効果が及ばない範囲である腰や臀部、下肢の汗の量が手術前より増える。ETSを行うと顔や手などの胸より上の部分の汗が止まるため、それより下の部分の汗の量が増える。ほとんどの患者に起こるが、代償性発汗を自覚しているのは約3分の2の患者。つまり、手術後には足の汗が増える可能性が高いということである。
直接の説明
ETSの内容、手掌からの発汗が止まること、ETSの副作用を説明。代償性発汗については、胸より上の汗が止まること、胸より下の汗が増えること、程度は人によって異なること、ETSを実施したほとんどの場合に代償性発汗が発症することを説明した。
代償性発汗の量がどの程度になるか、重篤な代償性発汗を発症することがあることについては説明をしなかった。
原告はホルネル症候群について最も気になっていて質問したところ、めったにないと回答した。代償性発汗で止まった部分の汗が体の他の部分から出るとは聞いていたが、出なくなる部分の汗がどのくらいの量であるかについては特に質問しなかった。
——————–
説明内容等に対する裁判所の判断
平成10年当時の発汗量の評価は、患者本人の訴えによる主観的な評価に依存している。手術後や治療効果を判定するためには客観的な評価が不可欠と考えられるが、その報告は少ない。
原告は、ETSで手掌多汗症が治ったこと自体には満足している。
適切な説明を受けていれば本件手術を受けていなかった、とは認められない。
平成10年当時にも、ETS術後に日常生活に支障があると訴えた患者はいた。当時NTT関東では手掌多汗症の患者が大量で手術は2年待ち。多数の手術経験があったと推認できる。ETSで重篤な代償性発汗が、ETSを行う医療機関の間で一般的な認識になっていたとまでは言えなかったとしても、NTT関東の医師においては、文献調査が十分可能であった。現に、平成7年までには、精神的に問題がある患者であったとはいえ、社会生活不能な事態に陥った症例や、ノイローゼになった症例を経験していた。
——————–
平成10年当時の発汗量の評価は、患者本人の主観的な評価に依存していたようです。そうすると、普通に考えれば代償性発汗についての覚悟を促す内容となっているこの術前説明は、その治療を受けるか否かの利害得失を検討するのに必要かつ十分な情報を提供したものと言って差し支えないでしょう。
さらに言えば、平成10年当時には、「ETSで重篤な代償性発汗が、ETSを行う医療機関の間で一般的な認識になっていたとまでは言えない」そうです。この点からも、「日常て生活に支障をきたすほどの代償性発汗を発症することがありうること」を説明しなかったことについて、過失を認めるには足りないと思われますし(裁判所もこの点での過失を認めているわけではないようですが)、多数の手術をこなしていたNTT関東病院での術後に社会生活不能な事態に陥った症例は、精神的に問題があった患者だというのですから、やはり「重篤な代償性発汗発症の危険性が一般に起こりうること」まで説明をしなかったからといって、過失を認めるということにもならなさそうに思います。
どうやら裁判所は、NTT関東(というかこの術者)はETSを多数行う専門性を持っていたのだから、文献調査を徹底的に行なってその危険性を伝えておかなければならなかった、ということを言っているようです。しかしこれも不思議なことで、ETSを多数行う専門性を持っているのであれば、どちらかと言えば情報提供側になることが多いと考えられますが、裁判所は逆のことを考えているのでしょうかね。医学的知見の拡散についての認識に、ちょっと無理があるように思いますがね。
なんにしても、この事例で無責判決(原告敗訴判決)ならば無理なくスッと書けると思われるのに、この判決は無理を重ねて有責判決に仕立て上げられた、いわば原告にいくばくかの花を持たせるように無理を重ねたと感じられて、いかがわしくて仕方がありません。
先日は判決文だけしか見れなかったので、後日、他の記録も見てみてから更に検討したいと思います。
手術を思い止まらせるのが説明義務なのか?
2011年11月25日
今年(平成23年)の6月に傍聴した事件と思われる、多汗症に対する手術の説明義務が争われた事件の判決が出たようです。事件番号は平成21年(ワ)第55号でした。
共同通信の配信によると、
判決は「ETSの後では、別の部位から多量の発汗があり日常生活に支障が出るなど、術前より苦痛を感じる場合があることを医師が説明していなかった」と過失を認めた。
と、説明不足があったという判断だそうです。
しかし、私が原告本人と、担当医師の尋問を両方聴いたところでは、手術そのものは成功して手掌の発汗は止まったそうですし、術前には代償性発汗の説明があって、原告本人も、乳首のラインより上から出なくなった分が乳首より下の部分から出るようになることを、術前に説明を受けて認識していたということでした。さらに言えば原告は術前に説明ビデオなどを渡されて、検討する時間も十分あったそうです。
それだけ説明してなお、「術前より苦痛を感じる場合がある」という説明が義務だという理由が、皆目見当がつきません。「乳首のラインより上から出なくなった分が乳首より下の部分から出る」という具体的な説明をしてありながら、なお「術前より苦痛を感じる場合がある」という抽象的な説明する義務を科すような判断というのは、我々の理解を超えています。
東京地裁民事第14部、高橋譲裁判長。以前からちょっとアレ気なところを感じていましたが、いくら何でもひどいんじゃないでしょうかね? 後日判決文を読んで、改めて報告することになると思います。
弁論終結の予定日に新証拠を出そうとする弁護士
2011年9月21日
平成23年9月14日の傍聴記です。まずは東京地裁民事第35部、事件番号平成23年(ワ)第25250号、第1回弁論。原告代理人のみ出廷。2年前にも代理人同士で直接相談したことがあり、時間が経ってしまった事案で、被告病院からはカルテがないので対応できない旨伝えられているという。医学的に簡単な事案ではないとも言われていた模様。当時の医師もいないと。今回、カルテがない旨の内容証明郵便も届いているとのこと。原告側、これで訴訟提起をして、やっぱりカルテが本当になければ、慶應病院などのカルテ等で一方的に理解して主張するかもというような話。訴状に対する被告側の出方次第だとも言う。無理じゃねーの?お次は東京高裁第23民事部、事件番号平成23年(ネ)第1909号、弁論。本日弁論を終結しようとしていたところに、控訴人(一審原告)が新証拠を提出した模様。それも医学的意見書か何かの結構な証拠らしい。被控訴人側からは、証拠採用をするならばこちらも準備して反論しなければならないので終結は困る、とのこと。裁判官3人合議のため一旦退出の後戻ってきて、「終結して、被控訴人の今の主張についても判決で判断をします」との旨を述べられた。つーことは控訴棄却でしょうw つーか終結の日に出すなよ。患者側弁護士とかが医療事故調とか騒いでいて、それはそれでいいんですど、弁護事故調も同時進行したほうがいいんじゃないですかねぇ?
まただよ@谷直樹弁護士@苫小牧市立病院の事例
2011年8月31日
例の、法的過失の理解が怪しい谷直樹弁護士のブログからですが、苫小牧市立病院,気管切開でカニューレが適切に挿入されず死亡した件で示談とのことです。
まずはお亡くなりになった女性のご冥福をお祈りします。
さてブログ記事によると、
市は「重大な過誤、過失はなかったが、気管切開手術が死亡要因であることは確か」としている。
とのことなのですが、病院側がそのように考えているとなると、少なくとも市側から進んで補償をすべき根拠はないと思われます。
ところが谷直樹弁護士によると、
厳密にどの行為に過失があったのかを具体的に特定することはできなくても,気管切開を行って,カニューレが適切に入らなかった(入れられなかった)という事情から,補償をすべきというのは,常識的な考え
だというのです。
示談金は500万円だそうですが、そのお金はもともとは市民の税金や病院の収入でしょう。脳出血で意識障害を起こし血腫の除去手術を受けたが、症状は改善されなかったという方の処置で、かつ重大な過誤、過失はなかったという事例に対して、金銭を支払って示談するのは如何なものでしょうか。苫小牧市民は、これによって市政や市民病院の診療原資が500万円分下がることに対して、疑問を抱かないのでしょうか。
このような例を見ると、いつも不思議に思います。
何が正しいのかわからない賠償判断
2011年8月24日
最近その存在を知って注視している、谷直樹さんという弁護士のブログがあります。
そこに、山形大学のカテーテル事故についての報告とそれに対する谷直樹弁護士の見解が掲載されました。
右室壁の穿通を引き起こしたことについて,臨床実務的に明らかな手技上の問題があったとは言えないが,「過誤」があった(すなわち,賠償する)との判定です. この判定の仕方は正しいと思います.
いや・・・
この判定のどこが正しいのか、何をもって正しいと考えているのかがよくわかりません。少なくとも、法的判断としては成り立たないものでしょう。つい最近、私のサイトで「手術の合併症と法的過失」について記事をアップしたところでした。
もしかすると、社会的にはそうあるべきという理想論を述べているのでしょうか。そうだとしたら紛らわしいですね。弁護士を名乗って書かれいているブログなのですから、「法的に正しい判断だ」と誤認されるおそれがありそうです。この記事を見て「この先生なら頼れる」と信じて依頼をして、裁判では案の定負けた、という人が増えないことを祈るばかりです。法律家としての説明責任が問われる記事だと思います。