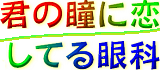令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
雑記2006
2006-5-1
産科医が訴えられるとき
感動的な母親救出劇です。この件では、医者はヒーローです。
しかし、もし母親が助け出されていなければ、遺族に訴えられていたかも知れません。業務上過失致死で刑事罰を受けるハメになるかもしれません。
いや、助け出されても、「子宮を摘出されるなんて聞いていなかった」などと言って訴えに出るような人も世の中にはいるようです。
先日、三重県尾鷲市の病院で、産婦人科医が年俸5000万円超で雇われたそうです。
24時間365日、心の休まる暇もなく精一杯やっても、なおかつ訴えられてしまう危険にさらされ続ける仕事を、あなたは年俸5000万円なら引き受けますか?
それがたとえ医者の仕事でなくても、僕なら絶対に引き受けませんね。
2006-3-22
日本の優勝を喜んだであろう或るアメリカ人について
2000年10月の雑記で或るアメリカ人の話を書いた。
----------------------------------------
シアトルのユースホステルでのお話。
15年ほど日本に住んでいたという40歳近いアメリカの女性が泊まっていた。日本語ができるのでいろいろ話したが,いつしか野球の話になった。
「私は巨人が大好きだった。巨人の野球を観に行って大声で応援したものだった。アメリカに戻ってきてからも野球は観るけれど,巨人を応援するように熱狂的には観れない。」
巨人のことを口にするだけで,遠い目になっているようだった。
「誰がやってた頃ですか?」
「最後の頃は監督が川上さんで,長嶋,王,藤田…」
「長嶋とか藤田はその後巨人の監督をやったんですよ。長嶋はいいときと悪いときがあったけど,藤田は優秀だった」
と,かつてのヒーローがその後も活躍していることを伝えると,言葉無く目が潤み出した。彼女にとっての強固なマイチームが,彼女が離れていた時間を超えて,連続性を見せながら彼女の琴線に迫ったのだろう。
彼女が今年の日本シリーズを観ることができていたならば,彼女はどんな気持ちで観ていただろうか…
----------------------------------------
今回のWBCで王貞治さんは、50歳を超えた彼女の前に、現役野球人として20年以上振りに再登場したことになる。そして、彼女は王ジャパンの準決勝の快勝を、そして優勝を、 普通のアメリカ人とは違って特別な喜び と共にたたえていることだろう。
2006-3-11
現実の対応
逮捕された産婦人科の医者が起訴されました。
将来的には、今回のような愚挙が起こらないように議論を重ねて法律を整備すべきでしょう。
しかし今の時点では、産婦人科医として分娩を扱うということは、常に逮捕・起訴の恐怖を味わいながら生きていくということです。
自分の人生を棒に振らないためには、事態が改善するまで、勤務医の場合は休職する、開業医の場合は休院する。
そう考えるのが普通だと思います。
2006-3-10
やめ、やめ!
いくらなんでも検察の頭が悪いでしょ?! そうでなくても死にそうな人を、助けようとして手を加えたら、やっぱり亡くなったっていって書類送検ですよ?!
医者なんて馬鹿らしくてやってられないでしょ?!
かくして内科・外科・産婦人科・小児科は減って、目医者ばかり増えるわけだ。
2006-3-8
医療崩壊の実例
内科医の救急輪番制崩れた山武地域で患者が長生病院に殺到(上の続報みたいなもの)
県立足柄上病院でお産が抽選か先着順に(神奈川)
その他のニュースへのリンクは「こちら」。(リンク集を提供してくださった方に感謝します)
勤務医が激務と心労でどんどん辞めてしまうのです。そうなる原因として、小児科での話ですが「子育ての医学情報」というサイトにちょっとしたまとめがあります。
2006-3-6
医者、怒る
以下の愚挙に対して、既にいくつかの団体から声明が出ていますが、神奈川県産科婦人科医会の発表(表紙はこちら)が、最も簡潔にまとまっていると思います。この問題は、日本の医療の様々な問題点が絡んで噴き出たものと考えられますが、私も気力があれば引き続き書きたいと思います。
2006-2-20
医療崩壊
本当に大変なことになっています。産科医療(というか医療全体)の崩壊がすぐそこまで来ています。こんな微妙な判断の治療で、犯罪的に実行したことでもない治療で逮捕されて、医者の間では「産婦人科はもうヤメだ」という声が渦巻いています。普通に仕事しても結果が悪ければすぐ1億2億の訴訟だったり、果ては 逮捕で、誰がやりますか?
ちなみに38歳の私の年俸は、目医者5年目で720万円。1億2億の訴訟にいつでもぶち当たる仕事であることを考えると、安い気はしますね。24時間休む暇のない産科や小児科ならなおさらです。産科小児科 医は減って当然です。